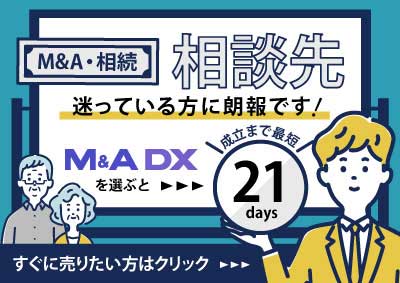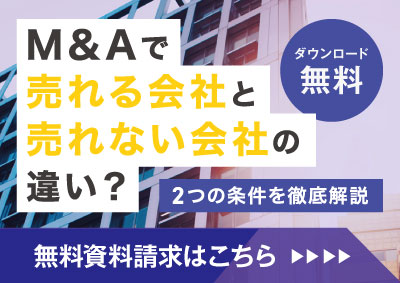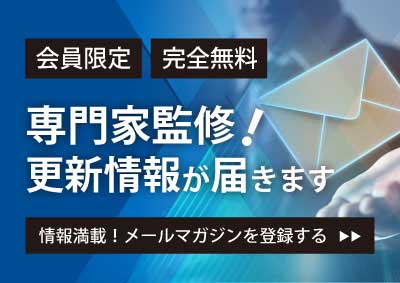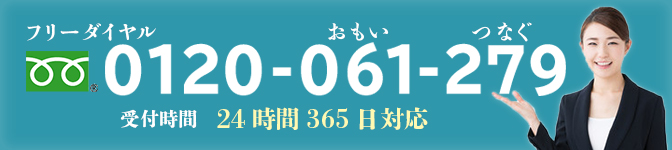吸収合併とは
吸収合併とは1社が存続して、ほかの会社を吸収する形で合併し、他の会社が消滅する合併方法です。例えばA社とB社が合併する場合にA社を残し、B社を吸収するとB社は消滅します。このとき消滅会社の権利義務は全て存続する会社に引き継がれるのが特徴です。
会社を丸ごと取り込む方法のため、権利義務について再契約する手間がかかりません。従業員との雇用契約を始め、さまざまな契約をそのまま承継できます。
また、存続する会社は、消滅する会社の株主へ対価の支払いが必要になりますが、対価は株式でも支払えるため、大きな現金を用意しなくても実施可能な統合方法といえます。
吸収合併の登記までにすること

吸収合併の準備から登記手続きまでを滞りなく進めていくためには、各ステップでやらなければならないことをきちんと把握しておく必要があります。ここでは、吸収合併の登記手続きまでにするべきことを順に紹介していきます。
1. 合併契約の締結
合併契約による効力が生じて無事に登記手続きを終えるためには、存続会社と消滅会社による合併契約の締結が大前提です。合併契約の締結前に、まずは両社で次のような項目の検討や交渉を行います。
・対価の内容や金額を検討、交渉
・対価の割当てに関する事項の検討、交渉
・吸収合併後の役職員の取り扱いを検討、交渉
各項目の検討や交渉が終了したら、会社法749条に基づいた合併契約を締結します。合併契約は、取締役会設置会社では取締役会決議、取締役会を設置していない会社では取締役の過半数の決定をしたうえで、当事会社の代表取締役が会社を代表して締結します。
2. 債権者保護手続き
合併契約の締結後は、債権者保護手続きをしなければなりません。債権者に対して官報公告と個別催告の2種類の方法を用いて、会社が吸収合併する旨を通知します。存続会社と消滅会社のいずれについても、債権者が異議を申し立てる期間として1か月以上を設けなければならないので注意しましょう。
公告を、官報に加え、定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞または電子公告によってもするときは、個別催告を省略できます。この方法は郵送にかかる手間を省けるため、催告者への通知漏れを防ぐのに効果的です。
吸収合併における被合併会社の手続きの流れ
被合併会社は合併会社との合併契約書を作成し、適切な流れで登記申請まで進めなければなりません。第一段階目に必要な手続きは合併契約の締結です。その後合併承認決議を行う流れで進めていきます。取締役会における合併承認決議では、以下の条件と方法がある点に注意しましょう。
・取締役会設置会社:取締役会決議
・取締役会設置会社以外の会社:取締役のうち過半数の決定
また、合併契約の締結・合併承認決議の順番は問いません。どちらも問題なく完了したあとは、事前開示書類を会社の本拠地に備えます。債権者に吸収合併の事実を公表するため、1ヶ月以上の異議申述期間を設けたうえで広告を行う流れが一般的です。
株主総会が実施される2週間前までに、株主に対する通知と広告を行いましょう。反対株主は、合併の効力発生日までの20日間にわたって株式買い取りを請求することが可能です。
株主から吸収合併が承認されると、契約書に記載された日程から効力が発生します。2週間以内に登記手続きを行いましょう。吸収合併に関する必要書類は、効力が発生してから6ヶ月のあいだ本拠地に備えなければなりません。以下は被合併会社に必要な手続きの流れです。
2.取締役会決議
3.合併契約の締結
4.反対株主に対する株式買い取り請求通知・公告債権者保護の手続き
5.吸収合併に関する書類の備置
6.株主総会にて承認を得る
7.吸収合併の効力発生
8.効力発生後の登記申請
【関連記事】合併とは?買収、統合との違いからメリットまで徹底解説!
【関連記事】吸収合併とは何か!必要な手続きや仕訳について
【存続会社】吸収合併における登記手続きの流れ

本格的に吸収合併の手続きを進めるには、複数の段階を経なければなりません。法律に則った方法で書類の記入や申請を行うため、不備のないようしっかりと確認しましょう。登記手続きは、存続会社と消滅会社では方法が異なります。ここでは、手続きの場所や書類について解説します。
登記手続きの場所
吸収合併によって存続会社となる場合、被吸収企業である消滅会社に関する書類も提出します。登記手続きを行う場所は、管轄の法務局です。合併後に増加した資本金の額をもとに、登録免許税を支払うことも覚えておきましょう。
登記手続きは、吸収合併の効力が発生してから2週間以内に済ませる必要があります。期限内に手続きができなかった場合、過料を請求されるおそれがあるので注意しましょう。効力発生日をあらかじめチェックして、なるべく早く手続きができるよう計画しておくと安心です。
変更登記申請書の提出
変更登記申請書を提出する前には、登記理由をはじめ必要事項に漏れがないか確認しましょう。記入する項目は法律で決まっています。具体的な項目は以下のとおりです。
・発行済み株式の種類
・発行済み株式の総数
・原因年月日
・資本金の額
・吸収合併の効力発生日
問題がなければ、収入印紙を貼付して提出します。
登記のための必要書類
変更登記申請書以外にも、さまざまな書類を提出しなければなりません。以下を参考に、必要な書類を用意しましょう。
・変更登記申請書
・吸収合併契約書
・登録免許税
・吸収合併に関する株主総会議事録
・債権者保護手続きに関する書類(公告及び催告をしたことを証する書面)
・消滅会社の登記事項証明書
・吸収合併に関する取締役会議事録
・資本金の額の計上に関する証明書
また、印鑑証明書や本人確認書類が必要になるケースもあります。変更登記申請を代理人に依頼するときは、委任状も用意しましょう。
【消滅会社】吸収合併における登記手続きの流れ
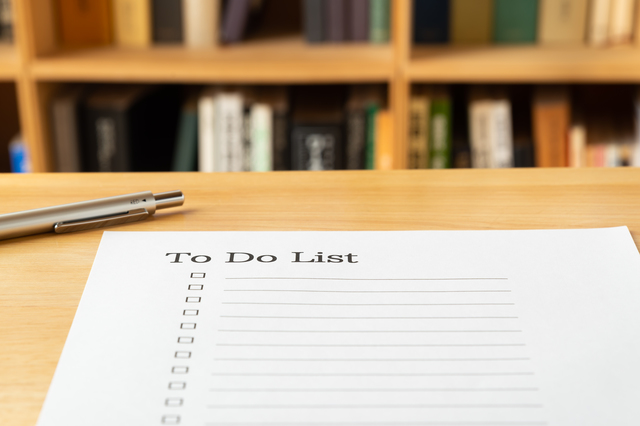
消滅会社の手続きは、存続会社に比べて必要な書類や行程が少なく済みます。しかし、書類を用意して記入する点は同じなので、スムーズな手続きができるよう流れを理解しておきましょう。ここでは、消滅会社の手続き場所や必要書類について解説します。
登記手続きの場所
消滅会社は変更登記申請書ではなく、解散登記申請書を提出します。提出する場所は、存続会社と同じく管轄の法務局です。ただし、清算結了登記を提出する場合は管轄エリアが異なる点に注意しましょう。
解散登記申請書は本店のみで問題ありませんが、清算結了登記は本店と支店それぞれの管轄で手続きを行う必要があります。手続きの行程が増えるため、余裕をもって進めると安心です。
解散登記申請書の提出
解散登記申告書は、吸収合併の効力が発生して2週間が経過するまでに法務局に提出しましょう。具体的には以下のような項目を記入します。
・商号
・本店の住所
・登記の理由
・解散する日付
・登録免許税の金額
・添付書類の内容と数
書面での提出が不安な方は、インターネットサイトからオンラインで提出することも可能です。また、電磁記録媒体でも手続きできます。
登記のための必要書類
消滅会社の手続きでは、解散登記申請書以外の書類は必要ありません。ただし、存続会社が以下の書類を変更登記申請とともに提出するため、早い段階でそろえておくと安心です。
・消滅会社の登記事項証明書
・株主総会議事録
・取締役会議事録
・債権者保護手続き書面
・登記を代理人に依頼する場合は委任状
登記事項証明書は、法務局またはインターネットサイトから取得できます。いずれの取得方法でも手数料がかかります。
吸収合併の登記に必要な費用

吸収合併の手続きには、収入印紙や登録免許税といった費用が必要です。資本金額によっては想像よりも額が大きくなることもあるため、あらかじめどのくらいの費用がかかりそうか計算しておいたほうがよいでしょう。一度に10万円以上を支払う場合もあります。ここでは、登記に必要な3種類の費用について解説します。
吸収合併契約書の作成
吸収合併契約書を提出する際は収入印紙代が必要です。契約書1通につき4万円なので、存続会社と消滅会社それぞれが用意する場合には合計8万円支払います。
ただし、登記の手続きに必要な契約書は1通のみなので、企業側が原本を2通以上用意する必要がないのであれば、写しを利用しても問題ありません。これだけで4万円の節約につながります。企業の数が多いほど収入印紙代も増えるため、何通用意するのか確かめておくとよいでしょう。
法定記載事項
吸収合併契約書の記載内容は、会社法で定められた項目があります。以下項目は、必ず記載しなければなりません。
1:合併当事者の情報
吸収合併契約書には、存続会社と消滅会社の商号と住所を明記します。
2:合併後の資本金と準備金に関する情報
合併後の資本金と準備金に関する情報記載も必須です。
3:合併対価の支払いに関する取り決め
消滅会社の株主への対価も明記が必要です。消滅会社が新株予約権を発行している場合、存続会社は新株予約権の数や金額、算定方法も記載します。
4:期日
施行される期日を明記します。
任意的記載事項
吸収合併契約書には、合意した重要事項を記載する場合があります。以下のような項目が、任意項目としてあげられます。
2:存続会社の取締役と役員の選任
3:消滅会社の株主の議決権
4:効力発生日までの増資や減資
5:人事に関する内容
6:吸収合併契約の効力
7:消滅会社の財産の引き継ぎ
8:その他吸収合併契約書に規定がない事項
登録免許税
登録免許税は、存続会社が支払う税金です。「吸収合併によってどの程度資本金額が増えたか」を基準に課税額が決まります。具体的な計算方法は以下のとおりです。
| 原則的な計算方法 | 増加した資本金額×0.0015 |
|---|---|
| 増加した資本金額が消滅会社の資本金額を上回る部分 | 資本金額の差額×0.007 |
| 税額が3万円以下または資本金額が増加しない場合 | 一律3万円 |
増加した資本金額の1,000分の1.5が原則的な登録免許税額となります。最低3万円と定められているため、資本金額が増加しなかった場合も3万円を支払わなければなりません。
通知のための公告費用
吸収合併契約を結んだあとは、一定期間公告を出す必要があります。債権者や株主に対して、吸収合併を行う旨を認知してもらうためです。具体的な方法は、以下の3種類から選択できます。
・日刊新聞
・電子公告
・官報公告(機関紙)
公告費用は、吸収合併の手続きを進めるうえで特に大金を費やすところです。方法や期間によって大幅に変動しますが、安価なケースでは5万円程度、高額な場合は数十万円に達することもあります。
吸収合併を行う際の注意点

吸収合併を進めるときには、リスクを考慮することも大切です。合併が必ずしも成功するとは限りません。存続会社が引き継いだ消滅会社のマイナス面が、経営に大きな影響を与えるおそれもあります。吸収合併に安心して取り組めるよう、三つの注意点をチェックしておきましょう。
実現しない場合もある
吸収合併の契約が確定するのは、双方の企業と株主が合意した場合です。企業同士が了承した場合でも、株主の反対で株主総会での承認が得られない可能性もあります。株式の買取を行った場合でも、吸収合併の手続きが進められないといった事態に発展するケースもあります。
このような結果になることを避けるためにも、あらかじめ協議や株主総会での票読みを重ねることが大切です。株主総会や取締役会のような場でしっかりと交渉しましょう。
マイナス面も受け継ぐ可能性がある
吸収合併を行う場合、「消滅会社が抱えるすべてを存続会社が引き継ぐ」という特性を理解しましょう。人材や技術といったプラス面だけでなく、思わぬトラブルや契約上の問題を引き継ぐ場合があります。
合併前に共有されている問題であれば改善策を検討できるものの、合併後に大きな問題が発覚した場合、最悪のケースで企業が継続できるか否かにもかかわります。消滅会社との関係性が悪化するかもしれません。トラブルに発展しないよう、マイナス面もすべて事前の協議で共有しましょう。
シナジー効果に関するリスク
吸収合併によって期待できる効果のひとつが「シナジー効果(相乗効果)」です。それぞれの企業の異なるノウハウや技術を共有することで得られますが、共有すること自体がリスクを生む場合があります。
そのため、システム、ルール、タスクといったすべてをひとつに統一する際には、慎重に進めなければなりません。統一がうまくいかなければ、効率だけでなく従業員のモチベーションを下げるきっかけにもなります。コミュニケーションを意識しながら、ストレスの軽減を目指しましょう。
吸収合併契約書
合併契約においては、必ず定めなければならない事項が法定されており、吸収合併の手続きにおいて当該法定記載事項を記載した書面を株主や債権者の保護のために備置する必要があります。
合併契約に規定すべき法的記載事項は、大まかに、「合併契約の内容」、「合併の対価」、「計算書類」、「効力発生日」等になります。
まとめ

吸収合併とはM&Aの手法のひとつで、複数の企業があるひとつの企業に吸収されることをいいます。法人格が残る存続会社と吸収される消滅会社の2種類が存在し、それぞれ手続き方法や流れが異なります。特に存続会社は必要書類が多いため、手続き時に不備がないよう事前に確認することが大切です。
合併によってさまざまなメリットが期待できますが、リスクがあることも覚えておきましょう。手続きを進めるうえで不安や疑問がある方は、ぜひ、M&A DXのM&Aサービスをご利用ください。M&Aや事業継承にかかわる専門家がご相談を受け付けています。
関連記事はこちら「合併(新設合併、吸収合併)とは|M&A・事業承継・相続はM&A DX ‐ madx」
関連記事はこちら「吸収合併とは?新設合併との違い・メリット・手続きを紹介」
関連記事はこちら「吸収合併で契約は承継されるのか?手続きの流れや注意点を解説」