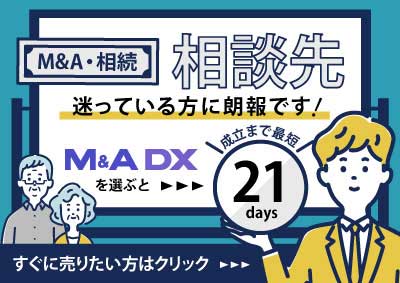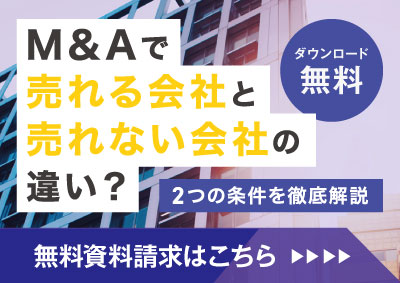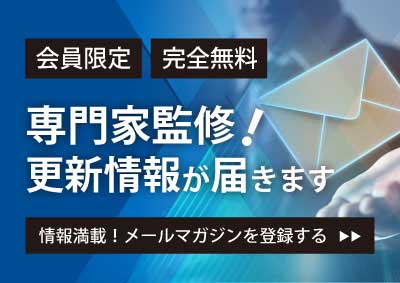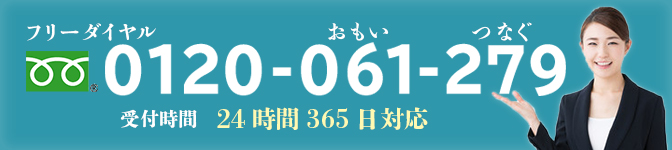合併とは

合併とは、2つ以上の企業がまとまって1つの企業になることです。買収の場合はそれぞれの企業が存続しますが、合併の場合は消滅する企業が出ます。
合併の手法には、「吸収合併」と「新設合併」の2パターンあります。合併すると、消滅する企業の債務や取引先との契約などはすべて、存続する企業や新設する企業に承継されます。「新設合併」は手続きが煩雑であることもあり、実務上は「吸収合併」のほうが多く活用されているようです。
合併契約書とは
合併契約書とは、合併契約を結ぶ際に作成する契約書のことです。合併契約書には、会社法上必ず記載しなければならない事項があります。
必要な記載事項が抜け落ちていたり違法な内容が記載されていたりすると、契約が無効になるので注意しましょう。
「吸収合併」と「新設合併」とでは必要な記載事項は異なるため、正確に把握することが重要です。合併後の円滑な経営を目指すうえでは、会社法で定めない任意の記載事項についても必要に応じて書き記すとよいでしょう。
合併契約書の項目別の作成方法

合併契約書は、おおまかな骨組みを守りながら作成します。どの項目に何を書くのかを把握し、書き方や注意すべきポイントについて丁寧に確認しながら進めるとよいでしょう。不備のない合併契約書が作成できれば、後のトラブル防止にもつながります。「吸収合併」と「新設合併」とでは必要な記載事項は異なりますが、今回は、実務上多く活用される吸収合併契約書を作る前提で解説します。
タイトル
会社法では、タイトルの詳細までは定められていません。「契約書」「合意書」「覚書」など、合併当事会社間の話し合いで自由に決められます。株主などに対する情報開示も踏まえ、取引内容がはっきりとイメージできるタイトルを選定するとよいでしょう。「吸収合併契約書」など、誰が見ても分かりやすいタイトルがおすすめです。
前文
前文には、どの企業が合併契約を結ぶのか、社名を記載しましょう。吸収合併では、存続会社と消滅会社が存在しますが、ここではそれぞれの社名を記載します。存続会社を甲、消滅会社を乙と記載するのが一般的です。
契約内容に関する定め
本文では、会社法が定める事項等について定めます。契約内容を書き記すときは、条文形式を用いるのが一般的です。条文形式とは「第1条、第2条、第3条……」と書き記す形式をいいます。
合併の方式や合併契約の効力発生日・従業員の処遇など、合併後の円滑な経営を左右する重要な項目です。ひとつひとつ確認しながら、慎重に作成しましょう。
合併契約書において、会社法上で必ず記載しなければならない事項については纏めて後述します。
結び
結びの項目は、合併契約の締結を証明する重要なものです。合併契約書の作成部数と、保管する場所について明確に記載します。存続会社と消滅会社が1部ずつ保管することを記載すれば、特に問題ないでしょう。
最後に、合併契約書の作成日を書き記し、続けて下に存続会社と消滅会社それぞれの住所・企業名・代表者名を記載して捺印しましょう。
添付書類
合併の最終的な手続きとして、存続会社の登記が必要となります。登記を行うにあたっては、合併契約書の他にも必要な書類が複数あります。合併契約書の準備とあわせ、これらの書類も準備するようにしましょう。準備を要する書類が複数あり、抜け漏れも発生しやすいので、専門家の指示を仰ぐことをお勧めします。必要な書類のうち主要なものを下記に記載します。
・合併契約書
・合併に関する株主総会議事録
・株主の氏名又は名称,住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)
・合併公告及び個別催告を行ったことを証する書面
・異議を述べた債権者に対し弁済若しくは担保を供し若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
・消滅会社の登記事項証明書
・株券提供公告をしたことを証する書面
・新株予約権証券提供公告をしたことを証する書面
・資本金の額の計上に関する証明書
・登録免許税法施行規則第12条第5項の規定に関する証明書
・取締役及び監査役の就任承諾書
・印鑑証明書
・本人確認証明書
・認可書(又は許可書,認証がある謄本)
・委任状
(参考:『商業・法人登記の申請書類:法務局』)
併契約書に必要となる項目は?

合併契約書を作成するうえで必要な項目は、どのようなものがあるでしょうか。項目の中には、「契約を有効にするために欠かせない項目」と「任意で記載する項目」があります。ここからは、どのような内容で吸収合併契約書を作成するかについて確認しましょう。
有効にするために欠かせない項目
合併契約を有効にするために欠かさず記載すべき項目が会社法で定められています。漏れがないよう把握しておきましょう。
①合併当事会社の商号と住所
②存続会社が消滅会社の株主や社員に対して株式その他の金銭等を交付するとき
- 当該金銭等が存続会社の株式であるときは、当該株式の数またはその数の算定方法並びに当該存続会社の資本金及び準備金の額に関する事項
- 当該金銭等が存続会社の社債であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額またはその算定方法
- 当該金銭等が存続会社の新株予約権であるときは、当該新株予約権の内容及び数またはその数の算定方法
- 当該金銭等が存続会社の新株予約権付社債であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額及び新株予約権の内容及び数またはそれらの算定方法
- 当該金銭等が存続会社の株式、社債、新株予約権以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額またはそれらの算定方法
③前記②の場合、消滅会社の株主や社員に対する②の対価の割り当てに関する事項
④消滅会社が新株予約権を発行している場合、存続会社が
- 新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる存続会社の新株予約権を交付するときは当該新株予約権の内容及び数またはその算定方法
- 前記の場合消滅会社の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、存続会社が社債にかかる債務を承継する旨並びにその承継にかかる社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額またはその算定方法
- 当該新株予約権者に対して金銭を交付するときは、当該金銭の額またはその算定方法
⑤前記④の場合、消滅会社の新株予約権者に対する存続会社の新株予約権または金銭割り当てに関する事項
⑥吸収合併が効力を生じる日
任意で記載する項目
合併契約書へ任意で記載する項目についても確認しましょう。必要に応じて下記のような項目を記載すれば、スムーズに手続きを進めることができ、トラブル防止にも繋がります。
・存続会社の定款
存続する企業の定款を変える場合に、変更後の定款を掲載しておきましょう。
・存続会社の取締役の選任
吸収合併に伴い新たに存続会社の取締役となるべき者の選任方法について記載します。例えば合併承認株主総会において選任する旨を書き記します。
・効力発生日までの資産状況の変化
消滅会社の資産に変化があった場合に、存続会社へ報告する旨を書き記します。
・人事に関する内容
消滅会社の取締役や従業員の処遇について記載することがあります。
・吸収合併契約書の承認
官公庁や株主総会から承認が得られない場合、契約が失効することを記載しましょう。
・消滅会社の財産の承継
効力発生日に消滅会社の全ての財産を、存続会社が承継する旨を書き記します。
・規定なしの事項
存続会社と消滅会社が協議を行ったうえで、合併に必要となった事項を記載するとよいでしょう。
M&A DXのサービスはこちら合併契約書を作成するうえで役立つポイント

合併契約書を作成する際には、会社法が定めていない事項でも書き記したほうがよい内容があります。ここでは、合併契約書を作成するうえで役立つポイントを解説します。
合併には吸収合併と新設合併がある
合併の手法には、「吸収合併」と「新設合併」の2つのパターンがあります。どちらも複数の企業が1つの企業になるという点では同じです。しかし、「合併後にどちらかの企業が存続するのか」と「対価への規定があるのか」については異なります。それぞれどのような特徴があるのでしょうか。
「吸収合併」とは、存続する企業の中に消滅する企業を取り入れる形で合併することです。会社法では存続する企業と消滅する企業が契約を結ぶうえで対価を規定すれば、株式以外であっても対価とできる旨を定めています。対価として現金を受け取ることができる手法はこちらの「吸収合併」です。
「新設合併」とは、2つ以上の企業がすでにある企業とは別に新たな企業を立ち上げることです。合併しようとするいずれの企業も消滅し、すべての権利義務が新しい会社に承継されます。会社法では「新設合併」での対価に対し、「株・社債・新株予約権ほか」と規定を設けているのが特徴です。対価として現金を受け取ることは出来ません。
権利義務を承継することを明記
権利義務の承継は会社法が定めるものであり、合併契約書に明記しなくても契約が無効になることはありません。
しかし、権利義務や財産などを承継するタイミングが不明瞭であることが原因で、企業間でトラブルが発生することがあります。どの日から権利義務の承継を行うのかを明確にするうえで、合併契約書に権利義務の承継について明記したほうがよいでしょう。合併契約書には4万円分の印紙が必要となる
合併契約書には、1部につき4万円分の印紙税が必要です<。存続会社と消滅会社とで合併契約書を計2通作成する場合、それぞれに4万円の印紙税が必要です。印紙税にかかる費用を抑えたい場合は、原本1通のみ作成し、その他必要部数を写しで対応することで対応すると良いでしょう。この場合、原本にのみ4万円の印紙税が必要ですが、写しには印紙税は発生せず、印紙税を総額で抑えることが可能です。
合併時に契約書の作り直しや契約再締結は必要ない
合併の場合、消滅会社が過去に締結済みの契約について再締結を行う必要はありません。
合併にあたり、消滅会社のすべての権利義務は、存続会社や新設会社に承継されます。消滅会社が取引先と締結していた契約についても、同様に承継の対象です。消滅会社の商号で契約が結ばれていますが、そのままで問題はありません。
ただし、契約に「チェンジオブコントロール条項」が付いている場合などは、契約再締結が必要になることがあります。消滅会社がどのような契約を結んでいたのか、合併契約締結前に予め内容を確認し、対応を協議しておきましょう。
契約締結は株主総会の前に行う
吸収合併契約の締結は、株主総会の前に行いましょう。なぜなら、吸収合併契約は「株主総会の承認を停止条件とする契約」と位置付けられており、株主総会の特別決議で承認を得る必要があるためです。
取締役会を設けている企業の場合は、取締役会決議を行った後に吸収合併契約を締結します。その後備置したうえで、株主総会の決議を行うのが一般的な流れです。
一方、取締役会を設けていない企業の場合は、取締役の過半数による決定が下された後に吸収合併契約を結びます。略式合併や簡易合併では、株主総会の承認が省略可能です。ただし、存続会社や株主にとって不利益が生じる場合は株主総会の決議が必要になる可能性もあります。
合併でわからないことがあればM&A DXの仲介サービスへ!
合併について自分で情報収集はできても、確実性の高い情報を抽出して活かすことは十分な経験がなければなかなかできません。不明点を解消してスムーズに合併を成立させるなら、M&A DXの仲介サービスがおすすめです。
M&A DXの仲介サービスは、初期的なプロセスである提携案件のFA・仲介業務からPMIプロセスまで一括対応できます。大手監査法人系M&Aファーム出身の公認会計士や税理士等が多数在籍し、合併に関する疑問や悩みをサポートするため安心です。合併に関してわからないことや不安なことがあれば、M&A DXの仲介サービスにご相談ください。
まとめ

「吸収合併」や「新設合併」するときに作成する合併契約書には、会社法が定めるさまざまな項目を記載します。項目によっては明記されていないと合併契約が無効になるものもあるため注意が必要です。また合併後の円滑な経営のためには、必要に応じて任意の項目も書き記すとよいでしょう。
M&A DXの仲介サービスは、合併に関する疑問点や不安を解消し、一括対応できるのが魅力です。合併を考えている方はぜひ一度、M&A DXの仲介サービスへご相談ください。