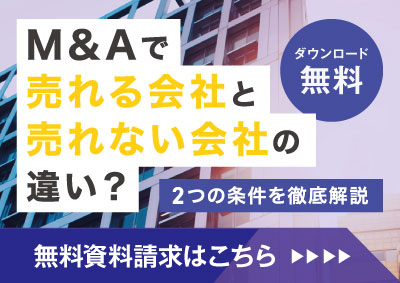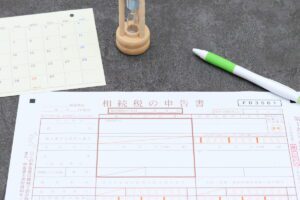2018年相続税法改正での遺留分の変更点
2018年7月に、民法相続法が約40年ぶりに大きく改正されました。この改正は、2020年4月までにすべて施行されています。
遺留分制度についても2つの大きな改正がありました。それぞれ解説します。
遺留分請求が金銭請求となった
従来、遺留分の請求は現物での返還が原則でした。たとえば、長男と二男のみが相続人である被相続人が遺言で全財産(2,000万円相当の土地、1,200万円相当の建物、800万円の預貯金)を長男に相続させるとした場合、遺留分請求の結果として二男が手にする財産は、原則として次のものだったのです。
<改正前>
・土地のうち4分の1の共有持分
・建物のうち4分の1の共有持分
・預貯金200万円(800万円×4分の1)
二男が遺留分の請求をすることによって、原則として遺留分を侵害した範囲で遺言の効力を失う(減殺される)ため、このようになっていました。結果として、土地や建物は長男と二男との共有になります。
遺留分請求をする人とされた人とではあまり関係性が良くない場合が多いにもかかわらずこれらの人で不動産を共有するため、不動産の利活用にあたってさらなるトラブルの原因となる場合があったのです。
こうした問題を受けて、改正により遺留分は原則として金銭請求となりました。
すなわち、上で挙げた例で二男が長男に侵害された遺留分を請求した場合、二男が受け取る財産は次のものです。
<改正後>
・1,000万円の金銭債権
※(土地2,000万円+建物1,200万円+預貯金800万円)×4分の1=1,000万円
改正により、二男は遺産の現物をもらうのではなく、長男に対して侵害された遺留分相当額の1,000万円を支払ってほしい旨の請求ができることとなりました。これにより、遺留分請求の結果として不動産が共有となる事態を避けられることとなったのです。
ただし、長男としては遺留分侵害額相当の現金を用意しなければならない点に注意が必要です。遺言で受け取った財産が金融資産ばかりであればまだしも、不動産や自社株など容易に換金できない財産が大半を占めていた場合などには、支払いに困窮してしまうかもしれません。
すぐに一括で支払えない場合には分割での支払いや支払期限の猶予を協議することとなり、当人同士で協議がまとまらなければ裁判所に決めてもらうことも可能です。
なお、遺留分請求が金銭請求となったことにともない、請求の名称も従来の「遺留分減殺(げんさい)請求」から「遺留分侵害額請求」へと変更されています。
相続人への生前贈与が10年以内のもののみへと制限された
遺留分の対象となる生前贈与については前編で解説しましたが、そこでは相続人への贈与のうち遺留分の対象となるものについて、次のように記載しました。
・共同相続人に対して相続開始前の10年間にした特別受益の贈与
この10年というのは、今回の改正で設けられた制限です。改正前は、共同相続人に対する特別受益の贈与であれば、期間の制限なくすべて遺留分計算の対象とされていました。そのため、たとえば30年前に受けた贈与を蒸し返して主張されることもあったのです。
しかし、現実的に見ればあまりにも古い贈与は資料が残っていないことや記憶があいまいであることも多く、期間の制限なく遺留分の計算対象になるとの取り扱いが争いの解決を難しくしていました。そこで、改正により10年という期限が設けられたのです。
自分の遺留分が侵害されている場合の対処法とは
たとえば遺言で自分の取り分が一切ない場合や極端に少ない場合など、遺留分が侵害されていると感じた場合には、どのように対処すれば良いのでしょうか。
ここでは、遺留分を侵害された際の対処法の例をご紹介します。
状況を把握する
はじめに、遺留分侵害について状況を把握することから始めます。ここで把握すべきであるのは、次の金額です。
・侵害された遺留分相当額
これを確認するためには、次の情報が必要となります。
・遺言の内容(誰がいくらの財産をもらったのか)
・遺産総額
・被相続人の債務の額
・生前贈与された財産など、遺産以外に遺留分の対象となる財産の価額
・自分の遺留分割合
遺産の額が多い場合や財産の種類が多い場合、他の相続人が生前贈与の状況を隠している場合などには、自分で調べることは難しい場合があります。この場合には、特に早い段階から弁護士へ相談しましょう。
遺留分侵害額請求をするかどうかを検討する
遺留分を侵害されたからといって、必ずしも遺留分侵害額請求をしなければならないわけではありません。
過去の事情や財産の内容などから見て自分の取り分が少ないことに納得ができるのであれば、遺留分侵害額請求をしないことも1つの考え方です。また、遺留分侵害額請求をすれば請求相手との関係性にヒビが入ってしまう可能性が高いため、相手方との今後の関係性を考慮して請求しない選択を取る場合もあるでしょう。
遺留分侵害額請求をすることから派生しうる長期的な影響を考慮のうえ、遺留分侵害額請求をするかどうか慎重に判断されることをおすすめします。
遺留分侵害額請求をする
遺留分侵害額請求をする選択をした場合には、期限に注意をして請求をおこないます。
遺留分侵害額請求の期限は、原則として相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知ってから1年間です。ただし、これらを知らないまま時間が過ぎた場合でも、相続開始から10年を経過するともはや請求することはできなくなります。
遺留分侵害請求の具体的な方法
遺留分侵害額請求をする方法は、次のとおりです。ステップごとに見ていきましょう。
ステップ1 内容証明郵便で請求する
遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害した相手(遺言などで財産を多く受け取った相手)に直接請求します。
その請求の具体的な方法は、法律で定められているわけではありません。そのため、口頭での請求や普通郵便での請求であっても、請求の効力は生じます。しかし、これでは「言った・言わない」の問題が生じる可能性があるほか、請求をした日時の証明も困難でしょう。
遺留分侵害額請求の最も重要なポイントは、期限内に請求することです。そのため、期限内に請求した証拠を残す目的で内容証明郵便にて請求をすることが一般的だといえます。
内容証明郵便とは、いつ、どのような内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを日本郵便株式会社が証明する制度です。
ステップ2 調停で請求する
内容証明郵便で請求をしても相手方が遺留分侵害額を支払ってくれない場合や、請求金額について双方の意見が食い違っている可能性もあります。たとえば、次のような事項について争いが生じる場合があるでしょう。
・遺留分計算の基礎となる遺産の範囲
・遺留分を算定するための遺産の評価方法
・生前贈与が遺留分の対象になるものかどうか
これらについて当事者同士で話し合いがまとまらない場合などには、調停をおこないます。
調停とは、家庭裁判所でおこなう話し合いのことです。調停には調停委員が立ち会って助言などをしてくれますが、調停委員が最終的な決断をくだすわけではなく、あくまでも当事者同士の話し合いで解決をはかります。
ステップ3 裁判で解決する
調停を経てもなお折り合いがつかない場合には、裁判へと移行します。
裁判では、裁判官が当事者双方の言い分を聞いたり資料を確認したりしたうえで結論をくだします。
途中で妥協点が見つかれば和解をすることも可能です。
遺留分トラブルを防ぐためのポイント
円滑な相続のためにせっかく遺言を作成しても、遺留分の請求でトラブルになってしまえば本末転倒です。遺留分のことをまったく考慮せずに相続対策をおこなってしまうと、財産を多く渡したかった相手を遺留分支払いの資金繰りで困らせてしまうことにもなりかねません。
ここでは、「相続人が長男と二男であるものの、長男に財産の多くを相続させたい」との前提で、遺留分トラブルを防ぐためのポイントを解説します。
遺言の作成は必須
遺留分の対策をする際には、まず遺言の存在が大前提となることを知っておきましょう。
苦心して遺留分の放棄などをしてもらったとしても、遺言の作成を失念したり遺言の作成が間に合わないうちに相続が起きてしまったりすれば、せっかくの苦労が水の泡となってしまいます。
遺言を作成する際には遺留分制度をよく理解したうえで、本当に遺留分を侵害した内容で作成するのか、二男にも遺留分程度の財産を渡す内容で作成するのかをよく検討をしたうえで作成しましょう。
付言事項やメモの活用
検討の結果、やはり遺留分を侵害する内容の遺言を作成する場合には、付言事項としてその理由や事情を記しておきましょう。付言事項とは、遺言に書き添えることができるメッセージのことです。
付言事項として記載する内容としては、たとえば次のような内容が考えられます。
・二男には事業開始時に金1,000万円を贈与した
・二男が家を買うときに金1,000万円を贈与した
・晩年に世話になった長男に財産を残すが、二男には私の遺志を尊重し、子同士で争うことはしないで欲しい。
遺留分に配慮しない遺言をつくる際には何らかの理由があるかと思いますので、その理由を付言に書き添えておくことで、二男の納得が得やすくなる効果が期待できます。
また、二男に対して多くの金銭的援助をしたことが理由なのであれば、遺留分侵害額請求をされた場合に備えてその証拠となる書類を保存するほか、金額や状況などを日記やメモなどでも残しておくと良いでしょう。
生命保険金の活用
遺留分を侵害する内容の遺言をつくる場合には、生命保険の活用も検討すると良いでしょう。
たとえば、被相続人が亡くなった際に長男が保険金を受け取れるようにしておくことで、長男が二男から遺留分侵害額請求された場合であっても、受け取った保険金を原資として請求された遺留分侵害額を支払うことが可能となります。
また、生命保険金は原則として遺留分計算の基礎となる財産に含まれません。そのため、同額の預貯金や現金を長男に相続させることと比べて、遺留分の金額自体を下げることが可能となります。
ただし、遺産総額から比して保険金の額があまりにも高額である場合には例外的に遺留分算定の基礎に含まれる場合もありますので、バランスには注意しましょう。
遺留分放棄の検討
二男に財産を渡さないことに合理的な理由があり、かつ二男自身が手続きに協力的である場合には、生前に遺留分を放棄してもらうことも検討すると良いでしょう。
しかし、たとえば単に念書などを作成しただけでは遺留分放棄の効力はありません。生前に遺留分放棄をするためには、家庭裁判所の許可が必要です。
また、遺留分放棄の許可は、所定の手続きさえすれば必ず認められるようなものではありません。一般的に、許可を受けるためには次の要件を満たす必要があるとされています。
・遺留分放棄をしようとする人の自由な意思によるものであること
・遺留分放棄の必要性や合理性があること
・遺留分放棄をしようとする人へ十分な見返りがあること
そのため、たとえば遺言者が無理に手続きをさせることや、単に関係性がよくないことを理由に放棄させることなどは認められません。
遺留分放棄の許可を受けるハードルは、低くないと考えたほうが良いでしょう。
廃除の検討
二男に財産を渡したくない理由が次のものである場合には、相続人からの廃除も選択肢の1つとなります。
・被相続人へ虐待
・被相続人への重大な侮辱
・その他の著しい非行
相続人の廃除とは、家庭裁判所に申し立てて審判がされることにより、その人の相続の権利を剥奪することです。非常に強い効果をもたらす手続きであるため、厳格な審査がなされたうえで判断されます。
廃除が認められればその人は相続権を失うため、自動的に遺留分の権利もなくなります。
ただし、廃除は代襲の原因となる点に注意が必要です。たとえば二男の廃除が認められたとしても、二男に子がいるのであれば二男の子である被相続人の孫が代襲して相続人になりますし、代襲した結果相続人になった孫にも遺留分の権利は存在します。
なお、廃除ができるのは遺留分のある推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき人)に限定されています。なぜなら、遺留分のない推定相続人であれば、廃除などをするまでもなく、単にその人に財産を渡さない内容の遺言さえ作成しておけばよいためです。
養子縁組などで相続人を増やす
請求される遺留分の金額を下げる方法の1つとして、養子縁組などで相続人を増やして、遺留分権利者の遺留分割合を薄めることを考える人もいます。
たとえば、法定相続人が長男と二男のみである場合の二男の遺留分は4分の1です。しかし、長男の子である孫を養子として相続人を増やすことで、二男の遺留分を6分の1に減らすことができます。
ただし、養子縁組は法律上の親子関係を発生させ、身分関係を大きく変える手続きです。仮にこの方法をおこなう場合には、二男の遺留分を減らすためだけの目的で養子縁組をすることは、縁組の目的に社会的妥当性がないことから無効になる可能性もあります。家族にとって本当に良いことかどうか、よく検討されてからおこなう必要があるといえるでしょう。
経営承継円滑化法における民法の遺留分に関する特例
遺留分が問題となりやすいケースの1つに、遺言者が経営する会社の自社株を保有している場合があります。自社株の評価方法については★【記事●】★で解説していますが、自社株には思わぬ高い評価がつく場合もあり、事業を引き継ぐ子に自社株を相続させようとすると、他の相続人の遺留分を侵害してしまいやすいのです。
しかし、自社株を売却してしまったり経営に関わらない子にも分け与えてしまったりすれば、経営の根幹を揺るがす事態にもなりかねません。
こうした場合に検討したいのが、「経営承継円滑化法」の活用です。経営承継円滑化法には、遺留分対策として次の2つの合意制度があります。
・固定合意:自社株が今後値上がりしたとしても、合意時点の価額で遺留分を計算する合意
・除外合意:自社株を遺留分計算の基礎から除外する合意
ただし、これらはいずれも遺留分のある推定相続人全員の合意が要件となっています。1人でも合意しない人がいる場合には、この制度を使うことはできない点に注意しましょう。
まとめ

特定の相続人に多くの財産を残す遺言を作成する際や相続対策をする際には、遺留分を避けて通ることは困難です。遺留分をまったく考慮せずにつくった遺言は、トラブルのもととなりかねません。
遺留分について正しく知り、必要な対策をしたうえで相続トラブルの原因とならないような遺言を作成するようにしましょう。