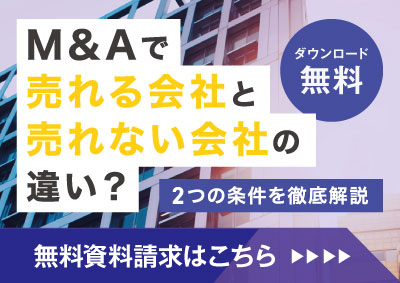2021年のM&Aの件数、傾向など
レコフデータの調査によると、2021年の1年間でおこなわれたM&Aは、4280件と、前年度と比較して14.7%の増加となりました。過去最多を記録した2019年の4088件を超えて、史上最多となりました。ちなみに、内訳としては、IN-INが最多の3337件、次いでIN-OUTが625件、OUT-INが318件です。
同社調査によるM&A件数は、2012年から2019年まで8年続けて増加してきましたが、2020年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により減少していました。2021年は、まだコロナの影響も残っていると思われますが、それでも過去最高件数を記録したということで、M&A市場全体に対する強いフォローウインドがうかがえます。
DXに向けたM&Aが増加傾向
2021年に過去最多のM&A件数を記録しましたが、特にIT業界に関連するM&Aが増加しています。増加要因の1つとして企業のDX推進が挙げられます。
日本のIT人材の約7割はベンダー企業に所属しているため、多くの企業がDXを推進するために必要なIT人材が不足しています。
そのため社内でDXを推進できるIT人材を確保することが重要視されつつあり、IT企業をM&Aで買収することでIT人材を確保する企業が増加しています。
2021年の代表的M&A事例10
続いて、2021年におこなわれたM&A事例から、10件をピックアップしてご紹介します。
事例1:セブン&アイ・ホールディングスによるスピードウェイの買収
セブン&アイ・ホールディングスは、2020年8月、米国企業「スピードウェイ」の買収を発表しました。スピードウェイはアメリカで第3位のシェアを誇るコンビニエンスストアチェーンで、ガソリンスタンドの他、食事、その他食料品などを一般消費者向けに販売しています。
当初、2021年1~3月の買収を目指しているとされましたが、米連邦取引委員会の承認手続きが長引いた関係で手続き完了が遅れ、最終的には、2021年6月に取得許可を得て、2兆3000億円という巨額の買収手続きを完了させました。2021年におこなわれたM&Aの中でも特に高額な譲渡価格で、注目が集まった案件でした。
もともと、米国の7-Eleven, Inc.は、コンビニエンスストア業界シェアが5.9%でしたが、このM&Aにより、セブン&アイ・ホールディングス全体としての全米のコンビニエンスストアのシェアは8.5%になると見込まれています。
このM&Aにおける統合シナジーは5億2000万ドルから6億2500万ドルほどになると、セブン&アイ・ホールディングスは見積もっています。
日本企業が米国のコンシューマー事業を買収して成功した事例は少ないといわれていますが、今回の巨大M&Aが成功を収めるのかどうか、期待と注目が寄せられています。
事例2:パナソニックによるブルーヨンダーの買収
2021年の4月に、パナソニックは米国企業のブルーヨンダー(Blue Yonder)を7,700億円で買収することを発表しました。セブン&アイ・ホールディングスによるスピードウェイの買収ほどではありませんが、こちらも巨額のM&Aになります。
一般消費者にとっては家電製品のイメージが強いパナソニックですが、BtoB領域ではデバイス・センシング・ロボティクスなど、インダストリアルエンジニアリングの技術とノウハウ、エッジデバイスやIoTを提供しています。
一方、買収されたブルーヨンダーは、グローバルに3000社以上の顧客企業を持ち、11億ドルの売上高(2021年)を誇る、世界最大のサプライチェーン・ソフトウェア専門企業です。デジタル・サプライチェーンとオムニチャネル・コマース・フルフィルメントの世界的リーダーであり、製造、物流、流通業の多くの大手企業様にエンドトゥエンドのプラットフォームやソリューションを提供しています。
このブルーヨンダーのサプライチェーン・ソフトウェアと、パナソニックのエンジニアリング領域での事業を組み合わせることにより、最終的には「オートノマス(自律的な)サプライチェーン」の実現を目指していくこととされています。生産現場のDX推進が求められる中、両社の統合は高いシナジーが発揮されるのではないでしょうか。
なお、パナソニックは2020年時点で、すでにブルーヨンダーの株式の20%を860億円で取得しており、取締役の派遣もおこなうなど、資本業務提携を進めていました。そして最終的に2021年9月に全株式を取得し、完全子会社化を実現しました。
事例3:ZホールディングスによるLINEの買収
2021年3月に、ZホールディングスとLINEの経営統合が完了した旨が発表されました。Zホールディンングスとは、YAHOOを中核としており、他にもZOZOや一休.comなどで形成されています。
今回の経営統合では、Zホールディングスの親会社であるソフトバンクと、LINEの親会社であるNAVERが共同で出資をおこなっているAホールディングスの下に、Zホールディングスを位置付ける形となりました。YAHOOとLINEは共に、Zホールディングスの傘下で対等な関係でこれからも事業をおこなっていきます。
今回の経営統合の狙いとして、「情報」、「決済」、「コミュニケーション」の3つの領域で事業を拡大し、オリジナルのいわゆる「経済圏」を形成することにあります。YAHOOは主に情報領域に強く、PsyPayという決済サービスも国内で広く使用されています。一方で、LINEはコミュニケーションツールとして国内でのシェアを獲得しており、LINE Payという決済サービスも保有しています。
これまでの「YAHOO経済圏」に、さらにLINEというコミュニケーションアプリが加えられたことで、いわゆる「楽天経済圏」と同等規模の経済圏を形成することに成功しました。
事例4:SBIホールディングスによる新生銀行の買収
SBIホールディングス(SBIHD)はTOBにより新生銀行の買収を2021年12月におこないました。これにより、新生銀行はSBIHDの連結子会社となりました。
新生銀行は旧日本長期信用銀行が破綻後に再生された銀行で、破綻時に国から支給された公的資金を返済途中の唯一の銀行です。公的資金を完済できていない理由として、歴代の経営者の経営方針が統一されていなかったことなど問題視されてきました。今回のTOBを通して新生銀行を連結子会社化したSBIHDは、新生銀行の経営層を一新し、まずは公的資金を完済すると発表しています。
一方、SBI HDは金融持株会社ですが、代表取締役の北尾吉孝氏は、かねてより「第4のメガバンク」を目指したいと公言していました。グループにはネット専業銀行の住信SBI銀行の他、地銀連合として多くの地銀に出資しているSBI地銀ホールディングスもあります。(今回のM&Aは、正確にはSBIHDとSBI地銀HDの両社によっておこなわれました)。
今後、新生銀行と住信SBI銀行の経営統合があるのかなども含めて、「第4のメガバンク」が実現するのか、注目されます。
事例5:マツモトキヨシによるココカラファインの買収
2021年の10月、マツモトキヨシホールディングスとココカラファインは経営統合をおこい、マツキヨココカラ&カンパニーが誕生しました。マツモトキヨシ、ココカラファイン共にドラッグストアや調剤薬局を展開している会社で、全国に多数の店舗を保有しています。経営統合に際しては、複数のM&Aスキームが使用され、ココカラファインがマツモトキヨシホールディングスの子会社となりました。
今回の経営統合の背景として、日本国内のドラッグストア市場内での競争の苛烈化が挙げられます。現在、さまざまな業種がドラッグストア市場に参入してきており、成長が困難になっている会社が多いです。
そこでマツモトキヨシとココカラファインは経営統合により、新商品の共同開発やデジタル販売戦略などを促進し、競争力とシナジー効果を高めるとことを狙いとしています。今回の経営統合で、2社合わせた業界シェアは1位となりました。
しかし、両者ともコロナウイルスの影響を受けて、直近の売り上げは減少傾向にあります。特に外出規制による化粧品の需要の低下と、インバウンド需要の消滅が大きな痛手となっています。ただし今後、人々の外出状況などが改善されれば業績も再上昇が期待されますが、新会社の動きに注目が集まります。
事例6:野村不動産HDによる庭のホテル東京の買収
2022年4月、野村不動産HDが「庭のホテル」を保有する株式会社UHMの全株式の譲渡による買収を実施。これにより株式会社UHMは野村不動産ホテルズ株式会社と合併されます。
野村不動産HDは不動産デベロッパーで各種不動産を取り扱っており、中長期計画の一環としてホテル事業にも注力しています。自社ブランドとしては「NOHGA HOTEL」を開発、保有しています。株式会社UHMは市場から高い評価を受けている「庭のホテル」ブランドのホテルを保有しています。
今回の経営統合の狙いとして、野村不動産が保有しているNOHGAホテルと庭のホテル、東京グリーンホテル間の相互送客や、既存の顧客基盤を活用したブランドの強化などが挙げられます。庭のホテルや東京グリーンホテル後楽園は、既に顧客から高い評価を得ており、ホテルとして事業も軌道に乗っています。さらに、UHM社が保有するホテル事業に関する豊富な内容を吸収、活用することで野村グループのホテル事業の競争力強化を目指します。
今後、野村不動産HDはこれまで以上にホテル事業に注力し、競合他社のホテルとも対等に競争できるようなホテル開発、ブランディングを目指します。そこで、「庭のホテル」で培われたノウハウが十分に役立てられるでしょう。
事例7:トゥールスによるビーイングの買収
上場企業であったビーイングが、2021年3月、経営者を同じくする親会社であるトゥールス(非上場)によりTOBで買収され、非公開化された事例です。このように、経営陣により株式が取得されて買収されることを、MBO(経営陣による株式買収)と呼びます。
ビーイングは建設業者を対象とした土木清算ソフトを販売している企業で、ジャスダック市場に上場していました。一方、トゥルース社はビーイング者の株式の約3割を保有する親会社で、持株会社の位置付けでした。両社ともに、代表取締役は津田誠氏です。
ビーイング社の経営は安定していましたが、建設業界でもDX化、ICT化が進行している昨今の状況で、土木清算ソフトウェアに依存していたビジネスモデルから、事業の多角化を計画していました。しかし、将来を見越した多角化投資であっても、短期的には財務が悪化する場合があります。それが株式市場で悪材料視され、株価が下落することもよくあります。株式市場からの評価を気にしなくてよい非上場企業のほうが、機動的かつ大胆な事業投資がやりやすい面もあるのは事実です。
そのような背景から今回のMBOが実施されたのです。これにより、ビーイング社のジャスダックへの上場は廃止となりました。
事例8:イオンによるキャンドゥの買収
イオンとキャンドゥは2021年10月に、イオンによる株式公開買付によるキャンドゥの連結子会社化をおこなう旨を発表しました。
キャンドゥは100円ショップで、スーパーやホームセンター、空港やドラッグストアまで様々な場所への出店に成功しています。一方で、100円均一ショップ業界では寡占状態が続いており、ダイソーが首位、セリア、キャンドゥ、ワッツがその後に続いています。
そのため、キャンドゥは連結子会社化を経て、イオンへの出店をおこない、100円均一業界でのシェア拡大を目指します。一方でイオン側も、キャンドゥの出店を受け、新規顧客の獲得と、商品ラインナップの強化を進めます。
このTOBによるシナジー効果は高くなることが予想され、両社の更なる業績拡大が見込まれるでしょう。 TOB公開後、キャンドゥの株価が高騰したことからも、市場における注目度も高いことが読み取れます。
事例9:ユニゾン・キャピタル系企業CHCP-HNによるN・フィールドの買収
いわゆるPEファンド(プライベートエクイティ・ファンド)などの投資ファンドが主体となったM&Aも年々増加しています。本事例は、投資会社ユニゾン・キャピタルが出資する株式会社CHCP-HNを通じて、東証1部に上場していた株式会社N・フィールドに対してTOB(株式公開買付け)を実施し、グループ化した事例です。
ユニゾン・キャピタルは、1998年に創設された国内系投資ファンドで、回転寿司チェーンの「スシロー」への投資などで有名になりました。投資対象として、コンシューマー事業、BtoB領域と並んで、ヘルスケア領域を1つの柱として掲げていることも特徴です。同社が以前から投資していたのが、ヘルスケア領域でさまざまな事業をおこなっている株式会社CHCP(地域ヘルスケア連携基盤)グループです。今回のTOBでは、そのCHCPグループの1社を通じて実施されました。
一方、N・フィールドは、2003年創業。精神科に特化した在宅訪問介護という、他にあまり類例をみないユニークな事業を47都道府県で展開。2013年に東証マザーズに上場し、2015年には東証1部に指定替えとなった急成長企業でした。
CHCPは、もともと地域での総合的なヘルスケアプラットフォームの構築を主要事業としており、N・フィールドとの連携は高い親和性があるといえるでしょう。
なお、TOBの成立後、2021年6月にN・フィールドは上場廃止しています。
事例10:ミダスキャピタルによる株式会社WAKUWAKUの買収
本事例も、買い手は投資ファンドです。ミダスキャピタルが運営するミダスファンドを通じて、2021年12月に株式会社WAKUWAKUの株式取得を行いました。
WAKUWAKU社は、2013年創業。建築・不動産業界のDX化を推進し、中古仲介とリノベーションのワンストップサービスを提供する事業モデルにより成長し、業界内で高く評価されていました。
また、株式会社ミダスキャピタルは、2017年創業と比較的新しい投資会社です。原則として上場後も投資先企業の議決権総数の35~50%程度以上を継続保有するなど、中長期目線での保有継続、リターン最大化を目指すことを投資理念として掲げているのが特徴です。
そのため、M&A後も、WAKUWAKU社の創業社長だった鎌田友和代表取締役はファンドの主たる組合員となり、引き続き、代表取締役かつ実質的な経営株主としてWAKUWAKU社の経営を担う形となっています。
ファンドから資金面やその他経営面でのバックアップを受けながら、創業経営者が引き続き経営にあたっていく形の成長型M&Aの事例です。
まとめ
M&Aがおこなわれる背景にはさまざまな事情があります。しかしここに取り上げた多くの例では、既存事業領域の強化、市場シェア拡大などの「攻め」のM&Aが多いといえるでしょう。「買収」と聞くとネガティブなイメージが持たれがちですが、こういった「攻め」のM&Aにおいては、売り手側企業の事業や従業員にとっても、ポジティブだと感じられるM&A結果になることが多いものです。今後、M&A譲渡売却などを検討なさっている方は、ぜひ参考になさってください。