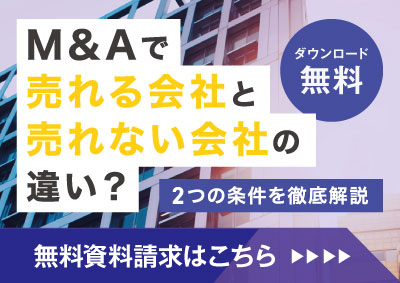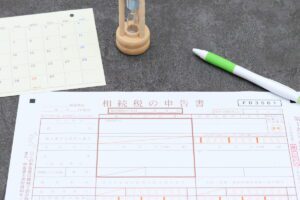生前贈与による相続税の節税効果
はじめに、生前贈与に関連する相続税と贈与税の基本的知識や、生前贈与による相続税の節税効果について確認・整理しておきましょう。
生前贈与により相続財産を圧縮することができる
生前贈与とは、文字通り自身が生きているうちに配偶者や子、孫などの親族に、自身の財産を贈与することです。
生前贈与をすれば、将来自分が死亡した後で、遺族にかかる相続税の負担を減らすことができる場合があります。
なぜかというと、相続税は亡くなった人(被相続人)の遺産に対して、それを相続や遺贈により受け取った方に課税される税金であり、遺産総額が減っていれば、その分相続税の負担は減ることになるのが原則だからです。
また、単純に遺産が減った分だけ相続税額が減るわけではありません。
相続税は、下の表のように、遺産の額に応じて税率が高くなっていく「累進課税制度」を採用しているため、遺産総額が減少することにより適用税率が低くなる場合もあります。
▼相続税の速算表
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
(出典:国税庁ホームページ)
生前贈与による遺産総額の圧縮と適用される相続税率の低下による相続税の節税効果を、簡単な事例で確認してみましょう。
・遺産の総額は7,000万円(生前贈与を考慮する前)
・法定相続人は子1人
この場合で、
(A)生前贈与をしない
(B)1,000万円の生前贈与をしている
(C)3,000万円の生前贈与をしている
のそれぞれについて、相続税負担を比較すると、以下のようになります。
▼生前贈与による相続税の節税効果
| ケース | 基礎控除額(注) | 課税遺産総額 | 相続税額 |
| (A)生前贈与していない場合 | 3,000万円+600万円×1=3,600万円 | 7,000万円-3,600万円=3,400万円 | 3,400万円×20%-200万円=480万円 |
| (B)1,000万円生前贈与していた場合 | (7,000万円-1,000万円)-3,600万円=2,400万円 | 2,400万円×15%-50万円=310万円 | |
| (C)3,000万円生前贈与していた場合 | (7,000万円-3,000万円)-3,600万円=400万円 | 400万円×10%=40万円 |
なお、「基礎控除額」とは、相続税額計算の際、遺産総額(課税価格の合計額)から差し引ける非課税枠です。基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算されます。遺産総額から基礎控除額を控除した金額が、課税される遺産=「課税遺産総額」となります。
(A)生前贈与しない場合に比べて、(B)1,000万円の生前贈与をしていた場合には170万円分の、3,000万円の生前贈与をしていた場合(C)には440万円分の相続税の節税効果があることがわかります。
これは、生前贈与により、相続税の課税対象となる遺産そのものが減っていることに加えて、適用される相続税率が低下していることも影響しています。
なお、相続税の詳しい計算の仕組みについて詳しく知りたい方は、以下のリンク先をご参照ください。
年間110万円までの贈与なら贈与税は課税されない
生前贈与をすることで、相続税の負担を減らせますが、では、可能な限りに多額に生前贈与をすればいいかといえば、そうでありません。贈与が行われた場合には、贈与を受けた人(受贈者)に対して、「贈与税」が課せられるためです。
詳しくは後ほど説明しますが、贈与税の税率は、基本的に相続税の税率よりも高く設定されています。(なお、贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがありますが、本記事では一般的に用いられている暦年課税を前提に説明します。)
生前贈与の節税効果については、相続税と贈与税とをセットで考えなければならないということです。
贈与税の基礎控除は、受贈者ごとに設定されている
贈与税には、受贈者1人当たりにつき、年間110万円までは課税されない「基礎控除額」が設定されています。
贈与税の基礎控除額は、「受贈者ごと」に設定されているものなので、例えば、ある人が、1年間に父から50万円、母から50万円の贈与を受けている場合、合計100万円で基礎控除額の範囲内となるため、贈与税は課税されません。
これを、贈与をする人(贈与者)のほうから見ると、多数の者に贈与をすれば、その人数分の贈与税の基礎控除が利用できるため、節税効果がその分大きくなると考えることができます。
例えば、1人に対して1年間100万円の現金を10年間にわたって贈与すれば、贈与税はゼロで、遺産総額を1,000万円減少させることができます。
同様の贈与を、受贈者3人に対して行えば、やはり贈与税はゼロで、遺産総額を3,000万円減らすことができます。
このように生前贈与を活用することで、相続税を圧縮することが可能になるのです。
なお、贈与税の基礎控除額は、配偶者や子などの将来の相続人への贈与に限らず、誰に対する贈与であっても適用されます。
「定期贈与」に注意!
ただし、上記の例のような場合には「定期贈与」に該当しないよう、注意する必要があります。定期贈与とは、毎年一定額の贈与を行うことが予め決まっている贈与のことです。
例えば、“毎年100万円を10年間にわたり贈与する”という内容の贈与契約を交わしたような場合は、この贈与契約を行った年に1,000万円の「定期金に関する権利」を贈与したものとみなされてしまい、受贈者にはこの1,000万円に対して贈与税が課されることになります。つまり、1,000万円の贈与を、分割払いにしたというように、みなされるということです。
もちろん、実際には上記のような内容の贈与契約を交わすことは少ないでしょう。しかし、それを判定するのは税務署です。そのため、ポイントは、「定期贈与」だと税務署に判断されないように注意することです。
具体的には、長期間にわたり生前贈与を継続していく場合には、毎年、同日に同額の振り込みをするといったことはしない、毎年、贈与の意思があったことを証明するため、その都度、贈与契約書を作成しておくなどの対応をしておくことです。
定期贈与について詳しく知りたい方は、以下のリンク先をご参照ください。
(参考)暦年贈与の活用方法と注意点!定期贈与や連年贈与とみなされないためのポイント
相続税と贈与税はセットにして節税を考える
贈与税は相続税よりも税率が高く設定されています。贈与税の税率は、以下の表のように2種類の体系があります。
ここで、下の表の「特例税率」というのは、18歳以上(令和3年3月31日までの贈与については20歳以上)の人が、父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受けた場合に適用される税率です。上の表の「一般税率」はそれ以外のすべての贈与に適用される税率です。特例税率は、一般税率よりも税負担が軽くなるように設定されています。
▼贈与税の速算表(暦年課税)
<一般税率の場合>
| 基礎控除後の課税価格(①) | 税率(②) | 控除額(③) |
| 200万円以下 | 10% | - |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
<特例税率の場合>
| 基礎控除後の課税価格(①) | 税率(②) | 控除額(③) |
| 200万円以下 | 10% | - |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
先に掲載した「相続税の速算表」と比べてみると、贈与税の税率はかなり高くなっているのがわかるでしょう。
このため、一度に(1年間に)多額の生前贈与を行った場合、同じ金額を相続させた場合よりも、税負担が増えてしまうことになります。財産額にもよりますが、生前贈与よりも、相続で財産を承継させるほうが、課税は少なくなるのが一般的です。
ただし、贈与税の基礎控除があるので、上述のように、時間をかけて生前贈与をすれば、遺産額を減らして相続税を圧縮する効果もあります。それが、相続税と贈与税をセットで考えるということです。
生前贈与で課税の総額が減る計算例
簡単な事例で検証してみましょう。
・被相続人の遺産総額は5億円(生前贈与考慮前)
・法定相続人は子供1人(相続税の基礎控除額=3,600万円)
(A)生前贈与をしなかった場合
(B)子に対して毎年1,000万円の生前贈与を3年間行っていたと仮定した場合
それぞれの場合の贈与税額と相続税額、税金総額は下表のようになり、生前贈与により約1,000万円の税負担軽減に繋がることがわかります。
贈与税を支払う方が結果的に節税となる事例
| ケース | 贈与税額(①) | 相続税額(②) | 税金総額(①+②) |
| (A)生前贈与しない場合 | 0円 | (5億円-3,600万円)×50%-4,200万円=1億9,000万円 | 1億9,000万円 |
| (B)生前贈与する場合 | {(1,000万円-110万円)×30%-90万円}×3年分=531万円 | (5億円-3,000万円-3,600万円)×50%-4,200万円=1億7,500万円 | 1億8,031万円 |
相続直前の贈与は税務調査で相続財産に戻される可能性がある
生前贈与によって相続税の節税を図る場合、忘れてはならない重要なポイントがあります。
それは、相続人が相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産については、相続税の計算上、その贈与はなかったものとして相続財産に含めなければならないというものです。これを「生前贈与加算」といいます。
つまり、相続人に生前贈与を行っていた場合、その贈与から3年以内に死亡してしまった場合には、その贈与は税額の計算上はなかったことになり、相続税の節税には繋がらないのです。
この相続開始前3年以内の贈与には、贈与税の基礎控除額以内(年間110万円以下)の贈与も含まれます。このことを知らずに、贈与について考慮せずに相続税の申告を行ってしまい、後の税務調査で指摘を受けるというケースもあるので注意が必要です。
なお、この相続開始前3年以内贈与の持ち戻し計算を行う場合、対象期間中の贈与について受贈者が収めた贈与税額は、相続税額の計算上、控除することができるので、二重に課税されるということはありません。
相続人以外への生前贈与は対象外
相続開始前3年以内贈与の持ち戻し計算の対象になるのは「相続又は遺贈により財産を取得した人」と定められています。
つまり、相続開始前3年以内の贈与であっても、相続でない人(例えば、子の配偶者、孫、甥、姪など)への贈与で、かつ、その受贈者が遺贈を受けないのならば、生前贈与加算の対象にはなりません。
相続が近いと考えられる場合には、相続人以外に生前贈与を行う方が、相続税の節税という観点からは効果的だといえます。
税務調査では、生前贈与された預金が「名義預金」ではないかを調べられる!
ここまで生前贈与による相続税の節税効果などについて説明してきましたが、生前贈与に対しては税務署も目を光らせており、怪しい点があれば相続税の税務調査などで追及されることになります。
一般的には、生前贈与は預金の振り込みで行われるでしょう。預金の生前贈与で怖いのは、税務署から生前贈与が認められず、被相続人の「名義預金」と認定されてしまうことです。
名義預金とは、「名義上の預金者」と「実質的な預金者」が異なる預金のことです。
例えば、銀行口座の名義人は被相続人の妻や子供であったとしても、実質的な預金者が被相続人である夫と判断された場合、その預金は夫の相続財産に含めなければならないことになります。こうなると、長年の相続税対策が水の泡となってしまいます。
以下では、生前贈与したはずの預貯金が、名義預金と認定されないよう注意すべきポイントについて説明します。
贈与契約が成立しているかが最大のポイント
預貯金の生前贈与が行われていた場合、被相続人と相続人との間で、「贈与契約」が有効に成立しているかが最大のポイントとなります。贈与契約の成立には、贈与者の“あげた”という認識と、受贈者の“もらった”という認識の双方が必要です(民法549条)。
例えば父親が幼い子供の名義の預金口座に、毎年贈与税の基礎控除額(110万円)の範囲内で送金をしていても、子供がそのことを知らなければ、贈与契約が成立しているとはいえません。このような状況のまま父親が亡くなった場合には、この預金は名義預金となり、父親の相続財産に含めなければなりません。
また、互いに“あげた”“もらった”という認識があっても、それが口頭による贈与の意思表示であるなど、後日贈与契約があったことを証明するのが難しい場合には、本当は贈与が行われていないのではないかと、税務署から指摘される可能性があります。
このため、贈与を行った場合には、たとえ基礎控除額の範囲内の贈与であっても、「贈与契約書」を作成しておいた方がよいでしょう。
また、基礎控除額を超える贈与をした場合には、贈与税の申告を行う必要がありますが、贈与税の申告を行っていたことは、贈与が成立していたと主張する有効な材料となります。そこで、あえて基礎控除額を超える額(例えば、年間120万円)の贈与をすることで、少額の贈与税を納税しておくことを薦める人もいます。
しかし、贈与税の申告が行われていたことをもって、必ず贈与が成立しているといえるわけではないことには注意が必要です。
例えば、子供が贈与を受けたことを知らないのに、親が代理で贈与税の申告を行っていたからといって、贈与が成立しているとはいえないということです。
預金通帳と印鑑は受贈者が保管する
この他にも、名義預金と認定されないために注意しておくことがあります。
まず、口座の預金通帳と印鑑、キャッシュカードは受贈者が保管し、自由に使える状態にしておく必要があります。その上で、時折預金を引き出したり振り込みに使うなどしておくと、自分(受贈者)のものであるとの主張を裏付けることができるでしょう。
なお、預金の受贈者が未成年のため、親が預金通帳と印鑑を保管しているような場合、子供が成人したら速やかに通帳と印鑑を渡しておく必要があります。
生前贈与以外の相続税節税方法
生前贈与以外にも相続税の節税対策の手法は多数あり、養子縁組で法定相続人を増やす方法や生命保険の活用などが挙げられます。
法定相続人の数が多いほど基礎控除額が増え、税負担が軽減されます。
基礎控除額は、簡単にいえば「税金がかからない額」ということで【3,000万円+法定相続人の数×600万円】です。養子縁組を行うと、養子は実子と同じ扱いとなり、法定相続人となるため、養子縁組によって法定相続人が増えれば、基礎控除額が増えて節税になるということです。
ただし実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人までになる点は留意が必要です。
また、生命保険を活用した節税では、保険料を被相続人自身が負担していた場合はみなし相続財産として、相続税が課税されます。
しかし、生命保険金には【500万円×法定相続人の数=生命保険金等の非課税枠】の非課税枠が設けられており、非課税額を超過した場合でも、超過した金額に相続税が加算されるため、生命保険は相続税対策に有効な手段と言えます。
まとめ
相続税を節税するために生前贈与を活用する際のポイントをまとめると、以下のようになります。
②長い年月をかけて
③可能であれば複数の受贈者に
④定期贈与にならないように気をつけながら
⑤相続発生3年より前までに
贈与する
生前贈与は相続税の節税に効果的ですが、節税効果を高めるには高度なタックスプランニングが必要です。また、生前贈与で財産の圧縮を図っていても、税務調査で名義預金であるなどと否認されてしまっては意味がありません。
税務調査で指摘されないためにも、生前贈与を行う際は、事前に税理士などの専門家に相談するとよいでしょう。