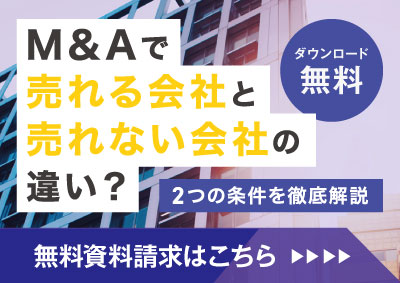相続時に発生する遺留分とは?

特定の相続人にすべての財産を遺したいと遺言書を作成したとしても、思い通りに財産を遺せないことがあります。相続財産には、一定範囲の相続人に対して相続財産の一定割合について相続権を保障する制度である「遺留分(いりゅうぶん)」があり、遺留分に満たない財産しか受け取っていない相続人が遺留分を求める可能性があるからです。
遺留分は、相続する人にとって大切な権利ともいえます。仮に遺言書によって相続人が何の財産も相続できないことになっていても、遺留分の範囲で財産の取得を主張することが可能です。
法定相続人に遺留分が発生する
遺留分は、法定相続人のうち、配偶者・子ども・直系尊属(親、祖父母など)に発生しますが、兄弟姉妹には発生しません。相続人が配偶者のみの相続では、配偶者がすべての財産を受け取ることになりますが、被相続人が配偶者以外に財産を遺すことを遺言書で示した場合でも、配偶者は財産の1/2を受け取ることが可能です。そのほかの例も参考にしてください。
| 法定相続人 | 法定相続分 | 遺留分 |
| 配偶者のみ | 1 | 1/2 |
| 配偶者と子3人 | 配偶者:1/2 子:各1/6 | 配偶者:1/4 子:各1/12 |
| 配偶者と親1人 | 配偶者:2/3 親:1/3 | 配偶者:1/3 親:1/6 |
事業承継時に発生する遺留分トラブルとは?

遺留分は、一定範囲の相続人に対して、相続財産の一定割合について相続権を保障する制度です。そのため、遺言書を作成するときは、遺留分を考慮して相続人や遺贈したい人に財産を分けるほうが良いでしょう。
しかし、相続する財産の中に会社株式が含まれているときは、特に慎重に検討する必要があります。
遺留分侵害
例えば配偶者と子どもが1人いる場合、本来の法定相続分では、遺産は配偶者と子どもが半分ずつ受け取ることになります。しかし、事業を承継する子どもにすべての財産を遺すと遺言した場合、配偶者は法定相続分である1/2はおろか、遺留分である1/4も受け取れません。このように遺留分の財産を受け取れない状態を「遺留分侵害」といいます。
遺言や生前贈与による特別受益
遺言がない場合は、遺産は原則として法定相続分どおり分けることになります。しかし、特別受益に該当するような生前贈与や遺言により、何らかの偏りのある分け方となったとしましょう。相続人によって法定相続分よりも多く受け取ったり、反対に法定相続分よりも少なく受け取ったりするため、不公平感が生まれるでしょう。
遺留分放棄
遺留分は相続人に保障された遺産ですが、相続開始前に、相続人の意思で放棄することも可能です。しかし、遺留分放棄をするときは家庭裁判所で許可を受けることが求められるため、口約束で「遺留分は放棄する」といっても効力はありません。もし、事業承継をしない相続人が遺留分放棄を申し出たときは家庭裁判所の許可を取得しましょう。
事業承継時と相続時の資産価値の変化
スムーズに代替わりを実現するために、経営者が元気なうちに事業承継をすることがあります。しかし、遺留分が発生するのは相続の時点であり、財産の評価時期は相続開始時であるため、事業承継時と比べて資産価値が変化しているときは注意するようにしましょう。
例えば会社の株式が1億円、その他の財産が3億円あったとしましょう。経営者の法定相続人は妻と長男、長女とします。長男が承継者になり1億円の株式を受け取り、その他の財産を妻が2億円、長女が1億円になるように生前に取り決めていたとしましょう。
この通りに相続が進めば、法定相続分通りに分けているので特に問題は生じません。しかし、経営者が亡くなり、相続が発生した時点で、長男が努力した甲斐もあり会社の株式の価値が9億円まで向上していたとしましょう。
妻は遺留分として3億円(12億円×1/4)、長女は遺留分1.5億円(12億円×1/8)の権利を主張するならば、長男は母親に1億円、兄妹に0.5億円、合計1.5億円もの財産を分けなくてはいけなくなってしまいます。長男の努力が報われるどころか、トラブルの種になってしまうこともあるでしょう。
事業承継時に活用できる遺留分特例

相続に遺留分があることで、事業承継がスムーズに進まないことがあります。特に遺産に占める事業関連の財産の割合が多いときには、承継者以外の法定相続人に遺留分を遺すことが難しくなるかもしれません。場合によっては、相続と同時に廃業する企業もあるでしょう。
こういった事態を防ぐために、「遺留分特例」があります。どのような制度か詳しく見ていきましょう。
特例が適用される条件
遺留分特例が適用されるためには、次の5つの条件を満たしていることが求められます。
● 推定相続人すべてから遺留分特例にかかる合意を得ていること
● 中小企業者であること
● 合意の時点で3年以上継続して事業を行う非上場企業であること
● 過去あるいは合意の時点で、被承継者が会社の代表者であること
● 現経営者から、贈与などにより株式を取得したことにより、会社の議決権の過半数を有していること
個人事業を承継する場合は、次の3つの条件を満たしていることが求められます。
● 推定相続人すべてから遺留分特例にかかる合意を得ていること
● 合意の時点で3年以上継続して事業を行う個人事業主であること
● 承継者に事業の用に供している事業用資産の全てを贈与したこと
除外合意
遺留分特例が適用されるためには、推定相続人すべてが合意をすることが求められます。合意には「除外合意」と「固定合意」の2つの種類があるので、それぞれどちらが適しているのか見極めてから合意の手続きをしていきましょう。
除外合意とは、生前贈与される株式等の全部あるいは一部を遺留分に含めないという合意です。除外合意を選ぶと当該株式等は遺留分算定基礎財産に算入されず、遺留分減殺請求の対象になりません。そのため、相続紛争のリスクを抑えつつ、後継者に対して集中的に株式を承継させられるというメリットがあります。
除外合意の例
経営者に妻と長男、長女がいて、法定相続人がこの3人のみの場合について考えてみましょう。経営者には株式が3億円、株式以外の財産が1億円あるならば、法定相続分と遺留分は以下のようになります。
| 法定相続人 | 法定相続分 | 遺留分 |
| 妻 | 2億円 | 1億円 |
| 長男 | 1億円 | 5,000万円 |
| 長女 | 1億円 | 5,000万円 |
長男が事業を承継し、生前贈与として株式3億円及び株式以外の財産1億円を受け取っていたとしましょう。このとき、株式について除外合意をしていると、遺留分算定基礎財産は1億円となるので、遺留分は以下のようになります。
| 法定相続人 | 遺留分 | 除外合意 |
| 妻 | 2,500 万円 | |
| 長男 | 株式3億 | |
| 長女 | 1,250 万円 |
固定合意
固定合意とは、生前贈与される株式等のすべてあるいは一部について合意時の評価価格で固定して遺留分を決める合意のことです。このように株式の価値を固定することで、相続発生時に株式の価値が上昇していても、遺留分の額に影響しないことから、事業承継者の経営努力により株式価値が増加しても想定外の遺留分侵害額請求を受けないというメリットがあります。
事業承継者としては、仕事を頑張れば頑張るほど相続できる財産が増えることになるので、モチベーション向上にもつながるでしょう。
固定合意の例
経営者に妻と長男と長女の3人の法定相続人がいる場合について考えてみましょう。事業承継する長男に株式1億円及びその他財産3億円を生前贈与したとします。
株式の評価額が変わらなければ妻は1億円、長女は0.5億円の遺留分侵害額を請求することになるでしょう。しかし、相続が発生したときには株式の価値が8億円増えて9億円になっていたとすると、妻は3億円、長女は1.5億円の遺留分侵害額を請求できることになります。
このような場合に備え、固定合意をしていると、長男は、株式の価値の増額分に関する遺留分を支払わずに済むでしょう。会社も存続させやすくなります。
| 法定相続人 | 固定合意しないときの遺留分 | 固定合意したときの遺留分 |
| 妻 | 3 億円 | 1 億円 |
| 長男 | ||
| 長女 | 1.5 億円 | 0.5 億円 |
遺留分特例の手続き

遺留分特例の適用を受けることで、事業をスムーズに次世代に引き継ぎやすくなります。特に遺産における事業財産が多い場合には、遺留分特例を用いて会社を引き継ぎやすい状態にしておくことができるでしょう。遺留分特例は以下の手順で手続きを行います。
1. 合意書を作成する
2. 経済産業大臣の確認を得る
3. 家庭裁判所の許可を得る
1.合意書を作成する
被相続人が生きているときに、事業の承継者に株式を遺すことを推定相続人全員に説明しておきます。そして、推定相続人及び後継者全員で、除外合意をするのか、固定合意をするのか等を決め、合意書を作成します。被相続人の意思を尊重することはもちろんのこと、財産状況や法定相続人の意見も取り入れ、合意書を作成しましょう。
2.経済産業大臣の確認を得る
推定相続人及び後継者全員で合意書を作成した後、その合意をした日から1か月以内に、後継者が経済産業大臣に対して、合意についての確認の申請を行う必要があります。
3.家庭裁判所の許可を得る
後継者は、経済産業大臣の確認を受けた日から1か月以内に、家庭裁判所に対して、遺留分の算定に係る合意の許可の申立てをする必要があります。許可の審判が確定すると、合意の効力が生じます。
まとめ

事業承継をスムーズに行うためにも、遺留分について考えておくことが求められます。遺留分特例を適用できるかどうかを調べ、適切に利用していきましょう。