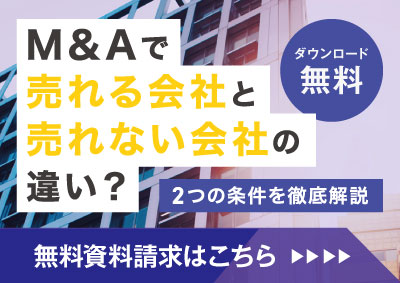寄与分とは
寄与分とは、被相続人の財産維持や増加に貢献した相続人が、他の相続人よりも多くの割合の相続財産分割を主張できる制度です。
なお、亡くなった人を「被相続人」、亡くなった人の財産を承継する人を「相続人」と呼びます。
民法では、どんな相続人がどのくらいの割合の遺産をもらえるのかの目安として、「法定相続分」という割合を定めています。しかし、法定相続分での遺産分割では、不平等に感じられるケースもあります。
例えば、相続人が3人姉妹で、長女だけが親の介護負担をすべて背負っていた場合に、その貢献が評価されないまま、次女、三女と同じ割合での相続分になるのは、疑問に感じらえるでしょう。
そういうときに、長女の相続分を貢献度に応じて増やすことで、公平性を保つことを図るために設けられているのが寄与分という制度です。

寄与分の主張から認められるまでの流れ
上記のような事情があった場合に、寄与分を認めるかどうかは、相続人間の話し合い(遺産分割協議)で決めるのが原則です。ただし、相続人間の話し合いでは解決できないこともあるでしょう。
話し合いが整わなければ、家庭裁判所での「調停」へ進みますが、調停も基本は話し合いなので、成立しないケースもあります。そうなると最終的には、「審判」によって家庭裁判所に決定してもらう流れになります。
さらに、審判にも不服の場合には、刑事裁判の控訴にあたる「即時抗告」を行い、高等裁判所から改めて審判を受けます。高裁の審判にも不服な場合には、特別抗告という方法もありますが、通常は行うことができません。高等裁判所の審判で確定になると理解してください。

寄与分を主張する前提要件
寄与分は誰もが簡単に主張できるものではありません。次の3つの要件すべてに該当していることが前提になります。
(1)相続人であること
寄与分を決める際、遺産分割協議がスタートであることからもわかるように、寄与分が認められるのは相続人だけです。被相続人の子の配偶者や、孫(子がいる場合)は、相続人にはなれません。また、婚姻関係のない「内縁の妻」や、ヘルパーさんも、もちろん、相続人にはなれません。これらの人が被相続人に貢献していたとしても、寄与分は認められません。
ただし、2019年の民法改定により、寄与分とは別に、「特別寄与料」という規定が設けられ(民法第1050条)、相続人以外の広い範囲の親族が、寄与に相当する金銭を請求できるようになりました。上記でいえば、この配偶者や孫は、「特別寄与料」を主張できる可能性があります。この点は後でくわしく解説します。
(2)特別の寄与であること
寄与分が認められるには、その貢献が、特別な寄与でなければなりません。この点が、寄与分が認められるか否かを判断する、もっとも難しい部分になります。なぜなら、社会通念上、家族や親族であれば、互いに協力して助け合うことは当然の行為だからです。親が高齢になれば、子や孫が生活の面倒をみるのは当たり前でしょう。
では、その当たり前の協力を超えた、「特別の寄与」と認められる行為はどのようなものなのでしょうか。
例えば、父が認知症になり10年間自宅介護を行っていた場合、その労力は並大抵なものではなく、特別の寄与だと認められる可能性が高いでしょう。
反対に、老人ホームに入所している父のところに10年間毎週着替えを持って行ったとしても、それは家族として当然の行為の範囲内と考えられ、特別の寄与として認められることは難しいでしょう。
(3)被相続人の財産の増加または維持に貢献する行為を行ったこと
その貢献によって、被相続人の財産が増加または維持されていなければ、寄与分は認められません。
例えば、子が父の家業を10年間手伝っていたとします。その手伝いによって売上が増大し、父の財産を明らかに増加させた場合には、父が死亡して相続が発生した際、子の寄与分が認められる可能性は高いでしょう。
反対に、一生懸命手伝っていたとしても不況によって売上は減り、父の財産も減ってしまったとしたら、寄与分が認められない場合もあるかもしれません。
なお、先の認知症介護の例などでは、自宅介護によって、その分、有料の介護サービスを受ける必要がなくなります。その費用が浮いたことで被相続人の財産が維持されたと考えられます。
特別の寄与といえるかどうかは、寄与行為の特別性、無償性、継続性、専従性などを総合的に考慮して判断していきます。
寄与分が認められる行為の5つの型
寄与分として認められる寄与行為は大きく5つの型に分けることができます。それぞれの内容と、認められる具体例を解説します。

(1)事業従事型
相続人が被相続人の事業を手伝っていた場合が該当します。農業、商店、病院、士業事務所など、どんな事業でも対象になります。
ただし、手伝いであればなんでも認められるわけではなく、以下の要件があります。
①無償ないし、無償に近い状態で行われていること
働いた分のお給料をもらっていたら、それは単なる労働であり、寄与にはなりません。
②長期間継続していること
一時的な手伝いでは認められません。
③かなりの負担を要するものであること
週に1、2回、1時間だけ手伝っていた、といった軽度の手伝いでは認められません。
特別な寄与によって遺産の維持管理に貢献をしたという要件を考えると、3年くらいは事業に従事していたことが必要になるでしょう。
(2)金銭等出資型
相続人が、被相続人へお金を援助、貸し付けた場合が該当します。
例えば、事業資金の援助や、自宅購入資金の貸し付けなどです。被相続人はそれによって銀行利息などが軽減され、財産を維持または増加することができたでしょう。
このケースでは、金額や内容などを総合して判断することになりますが、相続人が被相続人に対して生活費としてお小遣い程度の援助をしただけでは該当しません。
また、被相続人が経営する法人への出資の場合には、被相続人ではなく法人に対しての行為となり、寄与行為ではありません。注意しましょう。
(3)療養看護型
相続人が、被相続人の病気療養の世話や、介護をした場合が該当します。
例えば、寝たきりとなった被相続人の介護を自宅で行っていた場合などです。老人ホームや訪問介護サービスなどの費用を削減できているという点が重要になるため、その介護に要した時間や内容を記録しておき、浮いた介護費用を後で推計できるようにしておくとベターです。
(4)扶養型
扶養の必要性がある被相続人の生活費を、相続人が賄っていた場合が該当します。
例えば、年金受給者である被相続人の生活費のほとんどを負担し、年金は被相続人の財産として貯まり続けていた場合などです。
ただし、家族には扶養の義務があることから、扶養型での寄与分が認められるのは、まれなようです。相続人の一人だけが、長期間被相続人の生活を援助していたような場合が場合が該当するといえるでしょう。
(5)財産管理型
被相続人の財産を相続人が管理したことによって、財産が維持または増加した場合が該当します。
例えば、被相続人が所有している賃貸不動産の管理業務や清掃業務を相続人がしていた場合が典型です。管理会社に委託するとかかっていたはずの費用が浮き、被相続人の財産増加に貢献したとして寄与分が認められる可能性が高いでしょう。
なお、被相続人被相続人の資産を運用した結果として被相続人の財産が増えたとしても、原則として寄与分とは認められません。
相続人以外の寄与に対する特別寄与料
先にも触れましたが、2019年の民法改正により、「特別寄与料」制度が施行され、被相続人に特別の寄与をした相続人以外の一定範囲の親族(※)が、「特別寄与料」と呼ばれる金銭を請求できるようになりました。
よくあるのは、被相続人の子の配偶者(息子の嫁など)が、被相続人の介護をしていた場合です。このようなケースで相続が発生すると、子の配偶者は、民法上相続人とはならないため、法定相続分がなく、寄与分は認められません。
しかし、特別寄与料が創設されたことによって、このようなケースにおいて、相続が発生した場合、子の配偶者は、他の相続人に対して、特別寄与料を主張できるようになりました。
例えば、相続人が3人の子(長男、次男、三男)であり、長男の配偶者が特別寄与者である場合は、次男と三男に対して、特別寄与料を請求できるということです。

なお、特別寄与料の請求は、相続が開始したことおよび相続人を知った時から6ヶ月以内、または相続開始から1年以内に行わなければなりません。
(※)親族とは、6親等内の血族と3親等内の姻族をいいます。これだけの広さがあれば、一般的に付き合いのある親族は含まれているでしょう。

寄与分が認められた場合の相続分の計算
寄与分がある場合の相続分の計算は、通常の遺産分割と計算方法が少し変わり、次のような2ステップで計算します。
(1)遺産総額から寄与分に該当する金額を差し引き、残額を相続人全員で分割する。
(2)寄与分がある人には寄与分を足し戻す。
(遺産総額-寄与分)×法定相続分=相続分
【寄与分がある人】
(遺産総額-寄与分)×法定相続分+寄与分=相続分
計算例
次の条件における各相続人の相続分、および相続税計算の概略を示します。なお、下記の計算では、簡略化のため、「配偶者の税額軽減」以外の控除などはないものとします。
被相続人:父
相続財産:1億円
相続人:母、長男、長女
遺産分割方法:法定相続分
寄与分:長男に2,000万円

【各人の相続分の計算】
母 :(1億円-2,000万円)×1/2=4,000万円
長男:(1億円-2,000万円)×1/4+2,000万円(寄与分)=4,000万円
長女:(1億円-2,000万円)×1/4=2,000万円
【各人の相続税の計算】
1億円-基礎控除(3,000万円+600万円×3人)=課税遺産総額5,200万円
相続税の総額の計算
母 :5,200万円×1/2=2,600万円
2,600万円×15%-50万円=340万円
長男:5,200万円×1/4=1,300万円
1,300万円×15%-50万円=145万円
長女:5,200万円×1/4=1,300万円
1,300万円×15%-50万円=145万円
340万円+145万円+145万円=相続税の総額630万円
財産の取得割合に応じた各相続人の相続税額の計算
母 :630万円×4,000万円/1億円=252万円 (配偶者の税額軽減によって0円)
長男:630万円×4,000万円/1億円=252万円
長女:630万円×2,000万円/1億円=126万円
この場合の相続税は長男252万円、長女126万円の合計378万円となります。
○ 相続税の速算表
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
出所:国税庁Webサイト
寄与分が認められなかったとした場合の計算例
次に上の例で寄与分がなかった場合の相続税を計算してみましょう。相続税がどれほど変わるでしょうか。
【相続分】
母 :1億円×1/2=5,000万円
長男:1億円×1/4=2,500万円
長女:1億円×1/4=2,500万円
【相続税】
1億円-基礎控除(3,000万円+600万円×3人)=課税遺産総額5,200万円
相続税の総額
母 :5,200万円×1/2=2,600万円
2,600万円×15%-50万円=340万円
長男:5,200万円×1/4=1,300万円
1,300万円×15%-50万円=145万円
長女:5,200万円×1/4=1,300万円
1,300万円×15%-50万円=145万円
340万円+145万円+145万円=相続税の総額630万円
財産の取得割合に応じた各相続人の相続税額
母 :630万円×5,000万円/1億円=315万円 (配偶者の税額軽減によって0円)
長男:630万円×2,500万円/1億円=157.5万円
長女:630万円×2,500万円/1億円=157.5万円
この場合の相続税は長男、長女157.5万円ずつの合計315万円となり、長男への寄与分2,000万円がある場合の378万円と比べて63万円少なくなりました。
この計算例のように、寄与分の有無により、相続税の総額に変化が生じることもある点は注意してください。
寄与分が認められにくい理由
親の介護を一人で担う場合、「自分の貢献も寄与分で考慮されるべき」と感じる人が多いですが、実際の遺産分割では寄与分が考慮されることは少ないです。理由は3点挙げられます。
1 特別の寄与の要件が厳しいこと
要件の中でも特に「被相続人と相続人の身分関係(夫婦や親)から通常期待される程度を超える行為であること」がポイントで、寄与分を主張したいと考えている多くの方の認識と法律的な要件との間にズレが起きてしまいがちです。例えば、同居している親子であっても、普通はそこまでしないという場合には、「特別の寄与」として認められる可能性が高くなります。
2 証拠資料が不足しがちなこと
相続が起きたときに寄与分の主張をしたくても、それを裏付けるだけの資料がないためにほかの相続人や裁判官を説得することができず、寄与分の主張をあきらめざるを得ないケースも見受けられます。
3 感情的な対立を招きやすいこと
ほかの相続人とすんなりと話し合いが進むケースはごくまれで、裁判所での調停や審判で決着をつけざるをえないということもあります。
以上が寄与分が認められにくい理由です。
寄与分について、その他注意すべきポイント
その他、寄与分について、注意すべきポイントをまとめます。
寄与分と遺贈とでは、遺贈のほうが優先される
「遺贈」とは、遺言での指定によって、法定相続人以外の人に遺産を分割することです。
同じ相続において、寄与分の他に遺贈もある場合は、遺贈が優先されます。遺産総額から遺贈分を差し引いた残額から相続分の計算がスタートします。
(遺産総額-遺贈分-寄与分)×法定相続分=相続分
【寄与分がある人】
(遺産総額-遺贈分-寄与分)×法定相続分+寄与分=相続分
寄与分に時効はない
寄与分の主張に時効はありません。相続発生から何十年経っていても主張することはできます。
ただし、相続人全員が遺産分割協議に合意し、遺産分割が確定した後はその内容を覆すことは難しいことから、実質的に寄与分を主張できるのは遺産分割協議が成立するまでということになります。
また、実際上は、何十年も前の寄与行為を証明することも非常に難しく、時間が経てば経つほど認められなくなる可能性が高くなるでしょう。
なお、特別寄与料については、相続が開始したことおよび相続人を知った時から6ヶ月以内、または相続開始から1年以内という期限があります。混同しないように注意しましょう。
寄与分を主張しなくてもいいように、相続前に準備をしておく
寄与分は認められるハードルが高く、認められたとしても、希望金額より少ない金額となる場合が多いようです。その意味で、少し「使いにくい」制度だといえるでしょう。
一方、寄与分を主張したくなるほどの特別な貢献行為であれば、当然、被相続人も生前にそれを認識しているはずです。
そこで、可能であれば、寄与者の貢献に対して報いる方法を、被相続人の生前に検討しておくことがベターです。
例えば、遺言で遺産分割を指定してもよいでしょう。遺言なら、子の配偶者などへ遺贈を指定することも可能です。
あるいは、生前贈与で渡すという方法もありますし、生命保険を活用した方法もあります。
いずれの場合も、重要なポイントは、相続人全員が納得できるか、という点です。特別な寄与を受けたという事実、また、それに報いるための遺産分割割合の指定だということが、相続人全員に理解されなければ、相続人間でのトラブルの原因にもなりかねません。生前に相続人全員と話し合っておく、あるいは、被相続人の心情が伝わるような手紙を残すといった方法で十分に説明を果たし、トラブルを防止しましょう。
まとめ
寄与分や特別寄与料は、そもそも認定されるような内容なのかどうか、認定されるとしても、いくらなのか、他の相続人が納得するのかなど、非常に難しい側面が多々あります。
また、遺産分割協議が成立した後では、それを覆すことは、現実的には困難になります。そこで、もし「これは寄与分にあたるのだろうか?」と思うことがあれば、なるべく早く税理士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。