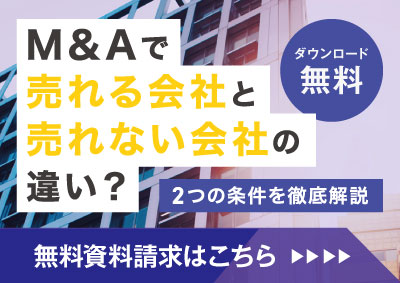相続における遺留分とは
「遺留分」とは、子や配偶者など一定の相続人に保障された、相続での最低限の「取り分」のことです。
たとえば、父、母、子の3人家族で、父が亡くなって相続が発生したとします。その際、父が遺言を作成していて、そこに「遺産の全てを子に相続させる」と書かれていた場合でも、母が相続できる財産は必ずしも「0」にはならない、ということです。このケースでは、母の遺留分は相続財産全体の4分の1になります。つまり、最低でも母は4分の1の遺産がもらえることが保障されているというわけです。
このように、遺留分に配慮しない遺言を作成すること自体は可能ですが、遺留分を持つ相続人は、「私には最低限保障されている相続権があるので、それだけは私にも分けてください」と、主張できるのが遺留分です。もし、この例で、母が子に「私には遺留分があるので、4分の1は私にください」と主張すれば、子はそれを拒むことはできません。
もし「嫌です」といっても、裁判等になれば、母の遺留分は必ず認められます。
そのため、トラブルを防止するためには、遺言を書く段階で、遺留分に配慮した遺言内容にしておくことです。
なお、遺言がない場合は、そもそも相続人の話し合い(遺産分割協議)で遺産分けをしますので、遺留分は問題になりません。
相続における遺留分の対象となる人、ならない人
遺留分は、相続人のうち一部の人のみが持っている権利です。そのため、そもそも法定相続人ではない人には遺留分はありません。
法定相続人について簡単に解説をすると次のような人です。
・配偶者相続人:被相続人の法律上の配偶者
・第一順位の相続人:被相続人の子。子が死亡している場合には、その子である孫やひ孫
・第二順位の相続人:被相続人の親。両親がともに死亡している場合は祖父母
・第三順位の相続人:被相続人の兄弟姉妹。兄弟姉妹が死亡している場合には、その子である甥や姪
これらのうち、遺留分を持つ人は次のとおりです。
・配偶者相続人
・第一順位の相続人
・第二順位の相続人
一方で、次の人には遺留分はありません。
・第三順位の相続人
つまり、被相続人の兄弟姉妹や甥姪が法定相続人となるケースであっても、これらの人には遺留分はないということです。
なお、次の人が存在する場合には、これらの人も原則として法定相続人に該当し、原則として遺留分もありますので注意しましょう。
・離婚協議中の配偶者
・養子
・海外に居住している子
・離婚した元配偶者が親権を持ち何十年も会っていない子
・認知した子
・他家に嫁いだ子
・他家の養子となった子(※)
(※)実親が養育できないなどの事情で幼い頃に他家の養子となった特別養子を除く
相続における本来遺留分の権利がある法定相続人でも遺留分が認められない場合とは
原則として遺留分の権利がある相続人であっても、次に該当する場合にはもはや遺留分の権利はありません。
・相続欠格者:法律に定める事由に該当したことにより自動的に相続の権利を失った人です。たとえば、故意に被相続人や同順位の相続人を殺害した人や、遺言を偽造したり、詐欺・強迫により遺言を書かせたりした人などがこれに該当します。
・相続人から廃除された者:被相続人への虐待など一定の事由に該当し、家庭裁判所の審判により相続の権利を剥奪された人です。これについては後編で解説します。
・遺留分を放棄した者:被相続人の生前に家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄した人です。こちらも後編で解説します。
・相続を放棄した者:被相続人の死亡後に家庭裁判所に自ら申述し、相続人ではなくなった人です。被相続人の借金を引き継がないことなどを目的になされることが多いです。
遺留分計算の基礎となる財産の価額とは
遺留分計算の基礎となる財産の価額は、次のように計算をします。
遺留分の基礎となる財産の価額=遺産総額+被相続人が贈与した財産の価額-債務
このように計算をした価額に、後ほど解説するそれぞれの遺留分割合を乗じて、各相続人の遺留分侵害額を算定します。
なお、計算式内の「遺産総額」には、次のものが含まれます。
・相続開始時の財産
まず、相続開始時に被相続人が有したプラスの財産は、遺留分の基礎となる財産に含まれます。
一定の生前贈与
次の生前贈与で贈与された財産も、遺留分の基礎となる財産に含まれます。亡くなる前に贈与で渡してしまえば遺留分の対象から外せるということではないため、注意しましょう。
・相続開始前の1年間になされた贈与
・(相続開始前の10年間にした)共同相続人への特別受益の贈与
・これら以前であっても遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与
共同相続人に対する贈与は「特別受益」の贈与との限定が付いていますが、たとえば事業資金のための贈与や住宅の贈与などはこれに該当する可能性が高いと考えられます。一方、たとえばギャンブルで使うための贈与であればこれに該当しない可能性が高いでしょう。特別受益に該当するかどうかは判断が難しい場合が多いため、迷った場合には弁護士へ相談されることをおすすめします。
また、贈与がたとえば「自宅不動産を贈与する代わりにローンの残額を支払ってほしい」などの負担付きであった場合には、贈与を受けた財産から負担の額を控除した金額のみが遺留分の基礎となる財産に含まれます。
ほかにも、たとえば「5,000万円の価値がある自宅不動産を子に1,000万円で売却した」など不相当の対価での譲渡の場合には、負担付の贈与と同様に評価額と対価の差額(例の場合には、5,000万円-1,000万円=4,000万円)が遺留分の基礎となる財産に含まれます。
相続における遺留分割合の計算方法
遺留分割合を算定する際には、まず、その相続全体での遺留分割合を確認します。相続全体での遺留分は、次のとおりです。
・第二順位の相続人のみが相続人である場合:3分の1
・その他の場合:2分の1
そのうえで、その相続全体での遺留分に、当該相続人それぞれの法定相続分を乗じて個々の遺留分を算定します。
では、具体的な例で見ていきましょう。
配偶者と子が相続人である場合
配偶者と長男、二男が相続人である場合、全体の遺留分割合は2分の1です。
これに、それぞれの法定相続分を乗じるため、それぞれの遺留分割合は次のようになります。
・配偶者:2分の1×2分の1=4分の1
・長男:2分の1×4分の1=8分の1
・二男:2分の1×4分の1=8分の1
たとえば遺留分計算の基礎となる財産が8,000万円であり、これを長男にすべて相続させるとの遺言があった場合には、配偶者と二男はそれぞれ次の額を長男に請求することが可能です。
・配偶者:8,000万円×4分の1=2,000万円
・二男:8,000万円×8分の1=1,000万円
両親のみが相続人である場合
被相続人に配偶者や子などがおらず、被相続人の父母のみが相続人である場合、全体の遺留分は3分の1です。これに、それぞれの法定相続分を乗じます。
それぞれの遺留分割合は次のとおりです。
・父:3分の1×2分の1=6分の1
・母:3分の1×2分の1=6分の1
たとえば遺留分の基礎となる財産が6,000万円であり、これをすべて内縁の妻に遺贈するとの遺言があった場合には、父と母はそれぞれ次の額を内縁の妻に請求することが可能です。
・父:6,000万円×6分の1=1,000万円
・母:6,000万円×6分の1=1,000万円
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
被相続人の相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合、全体の遺留分は2分の1です。
これにそれぞれの法定相続分を乗じた割合がそれぞれの遺留分となるのですが、そもそも兄弟姉妹には遺留分はありません。それぞれの遺留分割合は次のとおりです。
・配偶者:2分の1
・兄弟姉妹:なし
そのため、たとえば全財産を配偶者に相続させるとの遺言があった場合であっても、兄弟姉妹は配偶者に対して遺留分の請求をすることはできません。
これらを表にまとめると、次のようになります。
●図表1 遺留分割合のまとめ
| 全体の遺留分 | 個々の遺留分 | ||
| 配偶者 | その他 | ||
| 配偶者と子 | 2分の1 | 4分の1 | 子の合計が4分の1 |
| 配偶者と父母 | 2分の1 | 6分の2(3分の1) | 父母の合計が6分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 2分の1 | 2分の1 | なし |
| 配偶者のみ | 2分の1 | 2分の1 | ― |
| 子のみ | 2分の1 | ― | 子の合計が2分の1 |
| 父母のみ | 3分の1 | ― | 父母の合計が3分の1 |
| 兄弟姉妹のみ | なし | ― | なし |
相続における遺留分まとめ

前編では、遺留分の基本について確認してきました。
後半では、2018年に遺留分について改正された内容や遺留分を侵害された場合の対処法、遺留分トラブルの予防策などを解説します。