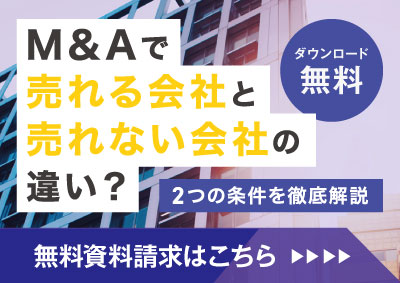【未上場株式の相続】「(3)納税資金を確保する」対策の基本
本記事では、非上場会社のオーナー経営者などが保有している自社の株式を「自社株式」と呼びます。
相続により、相続人に取得された自社株式は、相続税評価額で評価されて、相続税の課税対象となります。このとき、相続税は現金で納付しなければならないにもかかわらず、自社株式は簡単に売れない(現金化が難しい)という問題があります。
たとえば、相続した自社株式の相続税評価額が5億円、相続税額が1億円だったとすれば、納税には1億円の現金が必要です。自社株式で納税することはできまないのです。
しかし、多くの中小企業経営者の相続では、その相続財産の大半が自社株式になっていて、相続財産に現金があまりないことが多いのです。自社株式を相続した人はどうにかして納税資金を現金で用意しなければなりません。これがたとえば上場株式や不動産であれば、売却することは簡単にできますが、自社株は簡単に売ることができません。
そこで、自社株式が相続財産の中心となる場合は、納税資金の確保についても、十分に計画をしておく必要があります。
【未上場株式の相続】「(3)納税資金を確保する」対策の例
相続で自社株式を取得した人が、納税資金を準備するための代表的な対策には以下のようなものがあります。
生命保険を活用する
親であるオーナー経営者が契約者となって生命保険金に加入して、自社株式を相続する子が保険金を受け取れるようにしておきます。そしてその生命保険金を納税資金に充当します。保険金は相続人固有の財産であるため、遺留分の請求対象になりません。また、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠があるため、相続税額の計算上、直接現金を残すよりは有利になることが一般的です。
生命保険の活用法には、契約者(保険料の支払い者)が会社、被保険者がオーナー経営者となり、会社が保険金の受取人となる契約を結ぶ方法もあります。
そして、もしオーナー経営者が在職中に死亡した場合、保険金を原資とした死亡退職金を、自社株式を相続する相続人に会社から支払うように指示をしておきます。相続人は株式を引き継ぐとともに死亡退職金も受け取り、それを納税資金にします。死亡退職金にも、生命保険金と同様に、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠があります(生命保険とは別枠です)。
オーナー経営者個人で加入する生命保険と、会社で加入する生命保険から死亡退職金を支払う方法を併用すれば、両方の非課税枠が重ねて利用できるため、課税上さらに有利になります。
「金庫株特例」を使って、相続した自社株式を会社に売る
後継者が相続した株式の一部を会社に売り、その対価で相続税を支払う方法です。その際に課税上の特例として利用できるのが、「金庫株特例」です。
中編の記事で、会社が株主から株式を買い取って保管しておく「金庫株」について説明しました。そこで少し触れましたが、会社に株式を売った場合、出資金以上の譲渡対価部分は、原則的には「みなし配当課税」として総合課税になります。総合課税だと、最高で約50%の高い税率になることが難点でした。
しかし、相続で自社株式を取得した法定相続人がその株式を会社に売った場合は、いくつかの条件下では、その対価への課税を「株式譲渡益課税」とすることができます。譲渡益課税は、税率20.315%の分離課税となるため、総合課税と比べて税額をかなり抑えることができることがポイントです。また、金庫株特例を使う場合に、相続税額を株式の取得原価に加算して、収入金額から控除できる特例もあり、それを使えばさらに税額は低くなります。
この制度は、「相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例」といい、通称「金庫株特例」などと呼ばれています。
特例が適用できる要件は以下の通りです。
・相続税申告期限の翌日から3年以内(相続発生から3年10か月以内)に株式を譲渡すること。
・買い取る会社に配当可能な利益があること(債務超過状態などの場合は不可)。
【未上場株式の相続】国が事業承継を後押しするための「事業承継税制」
我が国の中小企業の後継者不足問題は深刻です。日本の中小企業のうち127万社(日本企業全体の3分の1)が後継者不在であり、このままだと、2025年までに約650万人の雇用と、約22兆円のGDPが失われる可能性があると指摘している経済産業省の資料もあります。
一方で、自社株式の評価が高くなりすぎて相続税の支払いが困難になることが、スムーズな事業承継の壁になっていることは従前から指摘されていました。そこで、円滑な事業承継を進めるため、2008年に制定されたのが「経営承継円滑化法」です。
同法は、何度かの改正を重ね、現在では、
・事業承継税制
・遺留分にかんする民法の特例
・金融支援
・所在不明株主に関する会社法の特例
の4本の柱で構成されています。
中でも、もっとも重要な柱となるのが「事業承継税制」なので、以下この税制について説明します。
なお、家族構成などによっては、「遺留分にかんする民法の特例」も適用したほうがいいような場合もあります。
【未上場株式の相続】事業承継税制を活用すれば、自社株式の相続税・贈与税の納付をしなくていい
事業承継税制をひと言でいうと、「事業を承継するために、後継者に自社株式を贈与または相続した場合、一定の条件の下で、相続税または贈与税の納付が猶予される」というものです。
ここで注意したいのは、原則的には、あくまで納税「猶予」であり、いきなり「免除」されるわけではない点です(一定の条件で免除される場合もあります。この点については後で説明します)。しかし、猶予だけであるにしろ、高額な相続税、贈与税を納付することなく、自社株式を承継できるれば、大きなメリットがあることは確かです。
なお、事業承継税制には、2008年の経営承継安定化法成立時に定められた本来の制度(一般制度)と、その後より使いやすいように要件緩和などがされた「特例制度」の2種類があります。
現在では、特別な事業がない限りは特例制度を使うことが普通なので、ここでも特例制度を前提にして説明を進めます。
事業承継税制適用の要件
事業承継税制を利用するにあたっては、「会社の要件」「経営者の要件」「後継者の要件」の3つの要件があります。ここでは、要件の主なものを掲載します。
会社の要件
・非上場の中小企業であること
・風俗営業、資産管理会社などではないこと
先代経営者の要件
・贈与の場合、贈与の時点で、会社の代表権を有していないこと(贈与の場合、すでに後継者に代表権を引き継いでいること)
・一族で50%以上の株式を保有しており、後継者を除いたなかで先代経営者がもっとも多くの議決権を保有していること
など
後継者の要件
・贈与の時点、または相続後の5か月以内に会社の代表権を有していること
・18歳以上であること
・一定期間役員に就任していること
・一族で50%以上の株式を保有しており、筆頭株主であること
など
上記からわかるように、すでに後継者が代表取締役に就任していることが、この特例の適用要件となっている点には、注意が必要です。
担保の要件
申告期限までに贈与猶予総額相当の担保を提供する必要があります。例として納税猶予の対象となる認定承継会社の特例非上場株式等です。もしくは不動産、国債、地方債、税務署長が確実と認める有価証券、税務署長が確実と認める保証人の保障などがあります。なお、猶予対象とした非上場株式はその全株式を担保とすることで贈与猶予総額相当の担保とされます。
事業承継税制適用の手続(概略)
・「特例承継計画」を策定し(認定経営革新等支援機関の確認が必要)、都道府県知事に提出して確認を受ける。
・贈与または相続後、一定期間内に都道府県の認定を受ける。
・認定書の写しを添えて贈与税または相続税の申告書を税務署に提出する
・その後、5年間(特例承継期間)は事業を続け、また、都道府県に対して報告書、税務署に届出書を毎年提出する
・さらにその後も、猶予を受け続ける場合は、3年に1度、届出書などを提出する
上記は概略で、実際にはいつまでになにをすべきか細かい締切が定められています。
贈与または相続の際に、1回認定を受ければそれで手続が終了するわけではなく、5年間は毎年、その後も3年ごとに書類を提出することが必要なのです。この手間が、事業承継税制利用のデメリットと感じる人もいるでしょう。
特例承認計画の提出は、2023年3月までの予定
本記事を執筆している2021年8月時点では、「特例承継計画」が提出できるのは、2023年3月31日までの予定です。それまでに、「特例承継計画」を提出しなければ、事業承継税制(特例制度)は適用できないことになります。「特例承継計画」は、認定経営革新等支援機関(認定された税理士など)の確認が必要であり、策定にある程度時間がかかります。
適用を受けたい場合は、時間的な余裕を持った準備が必要です。
適用後の贈与税・相続税はどうなるか
事業承継税制の適用を受けると、相続税の納付が猶予されます。猶予とは免除ではありません。では、猶予されている分が最終的にどうなるかというと、これは2つのバターンがあります。
猶予された税額が免除になる場合
・後継者が死亡した場合
・特例経営承継期間(5年間)の経過後に会社が破産した場合
・後継者が次の後継者に「免除対象贈与」をした場合
(「免除対象贈与」とは、贈与を受けた後継者が「非上場株式等についての贈与税の納税 猶予及び免除」の適用を受ける贈与です。)
など。
たとえば、親から子へ事業承継した際に事業承継税制を適用して贈与税が猶予されたとします。その後、特例経営承継期間(5年間)の経過後に、子から孫へとさらに事業承継がおこなわれ、株式を孫に贈与したとします。
その時に、孫が「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除」の適用を受ければ、猶予されていた贈与税が免除になるのです。
つまり、3世代にわたって2回の事業承継をおこなう場合、通常であれば、2回贈与税(または相続税)を納付しなければならないところ、事業承継税制を使うことで、親から子の贈与税の納税に関しては免除、子から孫の贈与税の納税に関しては猶予となります。
猶予されていた税の一部または全部を納付しなければならない場合
逆に、いったん猶予された税について、後から「納付しなさい」といわれてしまうこともあます。下記のようなケースです。
①特例経営承継期間(5年間)内について
・後継者が代表者を辞めた(やむを得ない理由がある場合を除く)
・一族の議決権が50%以下になった
・対象となった株式を売却した(一部の売却を含む)
・毎年義務づけられている届出をおこなわなかった
・本業を廃止した
など
②特例経営承継期間(5年間)後について
・対象となった株式を売却した(売却した株式の分のみ)
・本業を廃止した
・3年ごとに義務づけられている届出をおこなわなかった
など
上記からわかるように、特に特例経営承継期間(5年間)内については、厳しい条件が設けられています。そのため、事業承継税制の適用を受けるのであれば、後継者は、最低でも特例経営承継期間の5年間は、なんとしても事業を続けるという強い決意が必要です。
【未上場株式の相続】まとめ

中小企業オーナーの、未上場株式の相続税対策方法について説明してきました。しかし、ここに記したのはあくまでも基本部分のみです。
実際に対策を講じる際には、オーナー経営者の家族状況や資産状況、会社の状況などによって、千差万別の内容となるのは、当然のことです。そのため、自社株式にかんして適切な相続税対策を取るには、専門家の力を借りることが不可欠だといえます。
相続がいつ発生するのかわからないところが、相続税対策の難しいところ。嫌な話かもしれませんが、極端にいえば、明日事故で亡くなるかもしれないのです。
その意味からも、思い立ったが吉日で、早めに専門家に相談なさることをおすすめします。
前編記事「【中小企業オーナー必見】未上場株式の相続税対策方法_前編」
M&A DXが提供する【株価・事業承継対策】サービスの特徴
①経験豊富な税理士・会計士等の専門家が対応
<相談プロセス>
(1)株価算定を行い、事業環境を適切に把握
(2)把握した内容から対応すべき課題を探す
(3)対応すべき課題について、お客様の考えも踏まえた上で、お客様にとってベストなソリューションを提案する
②第三者への事業承継(=M&A)を希望する場合、
お相手候補の探索や、契約書作成業務までワンストップでサービスをご提供