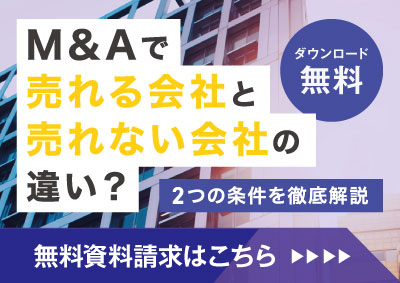貸倒れの計上方法には、直接償却と間接償却とがある
債権に貸倒れが起きた場合、あるいは債権の回収可能性がほとんどない(実質的に回収不能)と判断される場合には、会計上、会計帳簿にその貸倒の事実を計上処理することが求められます。
そして、その処理方法として、売掛金などの債権から貸倒損失額の全額を直接減額して、貸倒れ債権自体を帳簿から消滅させてしまう「直接償却」と、将来回収不能になると見込まれる金額を貸倒引当金に計上することにより、前もって費用化しておく「間接償却」(引当処理)とがあります。
直接償却は、簡単にいえば、「損切り」して、売掛金などの債権自体をなかったことにしてしまう方法です。
【債権の貸倒処理をする際(直接償却)の仕訳例】
貸倒損失 100 / 売掛金 100
債権が貸し倒れた場合の無税償却と有税償却
直接償却は、回収の見込みがない債権を、いわゆる「チャラ」にして、帳簿から消してしまう考え方であり、とくに難しいことはありません。
ただし、論点となるのが、この債権の貸倒処理をおこなった際、会計上費用となる貸倒損失が、税務上も損金算入できるのかという点です。
もし、税務上の損金算入が認められるのであれば、その金額部分には、法人税等はかからないこととなります。
税務上の損金算入が認められる債権の償却処理のことを債権の「無税償却」といいます。無税償却が認められれば、貸倒損失を計上した事業年度の税負担軽減(節税)につながるメリットがあります。
反対に、会計上費用として計上した貸倒損失が、税務上、損金算入できない場合、課税額を減らす効果は生じません。言い換えると、利益が減った部分の法人税も支払っていることになります。
そこで、このような税務上損金算入が認められない場合の償却処理のことを債権の「有税償却」といいます。
有税償却となると、貸倒損失計上事業年度の税額軽減にはつながりません。しかし、有税償却した金額分を、「繰延税金資産」として計上することができれば、将来的には法人税等調整額にマイナスを計上して課税額を減額できる可能性があります。(法人税を「先払い」しているイメージです)。
貸倒れに備えて引当金を計上することもある
将来の債権の貸倒れに備え、一定の要件(注)を満たす場合には会計上「貸倒引当金」の計上が求められます。
この場合には、債権の金額を直接減額させることなく貸倒引当金を計上し、相手勘定として貸倒引当金の繰入額を費用計上します。この貸倒引当金の計上のことを債権の「間接償却」と表現することもあります。
(注)将来の債権貸倒れによる損失の発生可能性が高く、その金額の合理的な見積もりが可能であることなどです。
【貸倒引当金を計上する際(間接償却)の仕訳例】
なお、貸倒引当金は、貸借対照表の負債の部ではなく、資産の部に「負」の金額で表示されます。つまり、貸倒引当金は負債ではなく、資産(債権)の評価額(のマイナス分)を適切に表すための勘定といえます。
そして、この貸倒引当金を計上する際にも、上記の貸倒損失計上の際と同様に、税務上無税償却か有税償却かになります。税務上定められている一定の要件を満たせば、貸倒引当金の繰入額が損金算入=無税償却できます。
▼貸倒損失(直接償却)・貸倒引当金(間接償却)を計上する場合の無税償却と有税償却
| 項目 | 区分 | 意味 |
| 貸倒損失 | 無税償却 | 会計上の貸倒損失が、税務上も損金として認められる |
| 有税償却 | 会計上の貸倒損失が、税務上は損金として認められない | |
| 貸倒引当金 | 無税償却 | 会計上の貸倒引当金の繰入額が、税務上も損金として認められる |
| 有税償却 | 会計上の貸倒引当金の繰入額が、税務上は損金として認められない |
貸倒損失計上時の無税償却の要件とは?
無税償却は、要件が定められています。
貸倒損失の認識を企業の判断に任せて、会計上の貸倒損失をすべて税務上の損金と認めてしまうと、利益操作などの不正が生じる温床ともなり、課税の公平性を損ねる恐れがあります。
そのため、法令や通達で貸倒損失を税務上の損金として取り扱うための要件が厳しく定められています。
税務上の貸倒損失は、「法律上の貸倒れ」、「事実上の貸倒れ」、「形式上の貸倒れ」に区分され、それぞれに詳細な要件や損金処理方法や損金算入額が定められています。それぞれの区分における要件等については下表のとおりです。
▼貸倒損失の損金算入(無税償却)が認められるための要件等
| 区分 | 要件(発生した事実等) | 経理要件・損金算入限度額 |
| 法律上の貸倒れ | 法令に基づく決定 会社更生法の更生計画の認可決定 民事再生法による再生計画認可の決定 会社法の特別清算の協定認可 関係者の協議決定(合理的基準による) 債権者集会の協議決定 行政・金融機関等の第三者のあっせん・協議による契約 債務者に対する書面による債務免除(債務超過が相当期間継続し、弁済不能と認められる場合に限る) | 損金経理(注1)の有無にかかわらず、次の金額が損金算入される ①・②の場合:切り捨て金額 ③の場合:債務免除額 |
| 事実上の貸倒れ | 債務者の資産状況、支払能力等からみて債権全額が回収不能となった(担保物のない場合に限る) | 金銭債権の全額(注2)を損金経理することにより、損金経理した金額が損金算入される |
| 形式上の貸倒れ | 継続取引のある債務者の経営が悪化したため取引を停止し、取引停止後1年以上経過した(担保物のない場合に限る) 同一地域の売掛債権の総額が取立費用に満たない場合において、支払いの督促をしても弁済がない | 売掛債権(注3)の金額から備忘価額(1円)を控除した残額を損金経理することで、損金経理した金額が損金算入される |
(注1)損金経理とは、(金銭債権について)会計上、費用または損失として処理することをいいます(上記仕訳例参照)。
(注2)事実上の貸倒れの場合、金銭債権の一部のみを損金とすることは認められません。
(注3)形式上の貸倒れの場合、対象となる債権は売掛債権に限定されており、貸付金やそれに準ずる債権は対象となりません。
貸倒引当金計上時の無税償却の要件とは?
貸倒引当金を計上する際(債権の間接償却をする際)にも、無税償却となるための要件が定められています。
税務上の貸倒引当金の概要
会計上の貸倒引当金繰入額についても、そのすべてを税務上の損金と認めてしまうと課税の公平性を損ねるおそれがあるため、法人税では、損金として取り扱うための要件が厳しく定められています。
なお、貸倒引当金の設定対象となる債権は、税務上、以下のように「個別評価金銭債権」と「一括評価金銭債権」に区分されますが、本記事では個別評価金銭債権について説明します。
| 債権区分 | 概要 |
| 個別評価金銭債権 (本記事の説明対象) | 一定の事実が生じていることによりその一部または全部について貸倒れによる損失が見込まれる債権で、損金算入要件や損金算入限度額が細かく定められている |
| 一括評価金銭債権 | 上記以外の一般金銭債権を意味し、損金算入限度額は、過去の貸倒れ実積率や税務上認められる法定繰入率を用いて算出する |
個別評価金銭債権についての貸倒引当金は、「2つの法的形式基準(①民事再生計画の認可決定など、②破産手続き開始の申立てなど)」と「実質的基準(債務超過状態が相当期間継続しているなど)」に区分され、それぞれに詳細な要件や損金算入額が定められています。それぞれの区分における要件等については、下表にまとめました。
▼貸倒引当金の損金算入(無税償却)が認められるための要件等
| 区分 | 要件(発生した事実等) | 損金算入限度額 |
| 法的形式基準① | 次の事象が生じたとき 更生計画認可の決定 再生計画認可の決定 特別清算に係る協定の認可の決定 私的整理手続における関係者の協議決定で次に掲げるもの 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの 行政機関、金融機関その他第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約で、その内容が上に準ずるもの | 債権金額から翌事業年度以降5年以内の弁済予定額を除いた残額 |
| ② | 次の事象が生じたとき 更生手続開始の申立て 再生手続開始の申立て 破産手続開始の申立て 特別済算開始の申立て 手形交換所による取引停止処分 電子債権記録機関による取引停止処分 | 債権金額の50%相当額 |
| 実質的基準 | 次のような事由により、金銭債権の一部の金額につき取立見込がないと認められること 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、その営む事業に好転の見通しがないこと 災害、経済事情の急変等により多大な損害が生じたこと など | 取立不能見込額 |
(注)いずれのケースにおいても、担保権の実行や保証債務の履行等による取立見込額がある場合には、それらの金額は貸倒引当金の対象となる金銭債権から除かれます。
貸倒引当金の無税償却が認められるのは、税務上の中小法人等のみ
なお、税務上貸倒引当金の無税償却(損金算入)が認められるのは、基本的に税務上の「中小法人等」に限定されています。中小法人等とは、主に、資本金が1億円以下の法人です(資本金が5億円以上である法人の完全子会社は除く)。
中小法人以外の法人が貸倒引当金を計上しても、その繰入額は損金不算入(有税償却)となってしまう点に注意が必要です。
会計と税務の、貸倒引当金に対するスタンスの相違
ここで、企業会計上と税務上(法人税)との貸倒引当金に対するスタンスの相違について触れておきます。
純粋な企業会計においては、上記とは異なる基準で貸倒引当金(または貸倒損失)の計上を求めています。端的には、より早期により大きい金額の引当金等の計上が求められると考えればよいでしょう。
たとえば、取引先が自己破産の申し立てをした場合、上表内の「法的形式基準②」に該当し、債権金額の50%相当額までの貸倒引当金繰入額の損金算入が認められます。
しかし、現実的には、自己破産を申し立てた取引先への債権の50%相当額を回収できることはほぼ不可能です。このような場合、会計上は債権の全額(取立見込みのある部分を除く)について、貸倒引当金を計上する(あるいは貸倒損失として直接償却してしまう)ことが適当です。
上場企業や会社法上の大会社など、外部からの会計監査を受けている会社であれば、上記のように、税務上の基準とは異なる基準で貸倒引当金の計上がおこなわれることがあります。
一方で、会計監査を受ける必要がない中小企業では、税務上の規定の要件や限度額にあわせて、個別評価金銭債権にかかる貸倒引当金を計上することが一般的です。
最近の無税償却の動向
2013年の税制改正により、それ以前では認められていなかった金融機関での債権放棄時の無税償却が新たに認められるようになりました。この税制改正により金融機関は債権放棄を積極的に認めやすくなり、中小企業の再生が活発化しました。無税償却は、中小企業の再生を促進する重要な制度となっています。
グループ会社などへの債権の場合は「寄附金課税」に注意
ここまで、通常の商流の中で生じた売掛金など、基本的に第三者との取引により生じた債権を前提に説明をしてきました。
しかし、債権の中にはグループ会社やオーナー一族などへの貸付金などが含まれる場合があります。このような、いわゆる“身内”に対する債権については、債務者が債務超過状態であるため債権が回収不能であるなどの理由で「債権放棄(債務者からすれば債務免除)」をしたとしても、税務上この債権放棄損(貸倒損失)が「寄附金」と認定されるおそれがあることに注意が必要です。
寄附金と認定された場合、一般的には損失額の大部分が損金不算入とされ、また、債務者には受贈益課税や給与課税等がなされることになってしまいます。
ただし、寄附金認定された場合でも、法人による完全支配関係がある場合には、いわゆる「グループ法人税制」の適用があるため、課税関係が繰り延べられることになります(詳細は本記事のテーマから外れるため割愛します)。
なお、上記のような債権放棄損であっても、子会社等の解散や再建を目的とする債権放棄であって、税務上の所定の要件を満たすものは寄附金に該当しないこととされています。この点についての詳細は、以下のリンク先の国税庁ホームページなどを参照ください。
国税庁ホームページ:法令解釈通達「寄附金の範囲等」
まとめ
債権の貸倒損失や貸倒引当金の設定、また、それらが無税償却できるのか、有税償却しなければならないのかは、企業の財務やキャッシュフローに大きな影響をもたらします。
税務上の損金算入要件は上記のように厳しく規定されており、これを踏まえどのような会計処理をおこなうかは、税理士などの専門家に相談しながら慎重に判断しなければなりません。