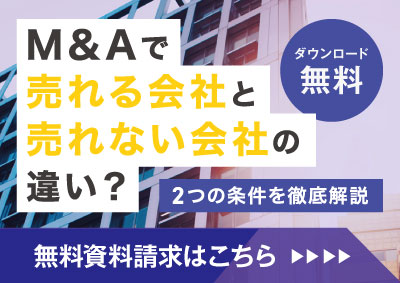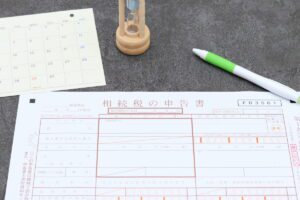民法改正とは

そもそも、民法改正自体は珍しいことではなく、数年に一度必要に応じて国会で可決された上で施行されています。今回解説するのは、2018年7月6日に成立した「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」並びに「法務局における遺言書の保管等に関する法律」についてです。まとめて「改正相続法」とも呼ばれます。
成年年齢の引き下げと相続法が改正
2018年に成立した民法改正は「成年年齢の引き下げ」、「相続法改正」という個人にも強くかかわる分野です。まず成年年齢の引き下げとは、満18歳に達する日から成年とするもので、これにより満18歳からは単独で法律行為ができるようになります。なお、成年年齢の引き下げが施行されるのは2022年4月1日からです。
相続法改正も同時期に成立していますが、施行日はそれぞれ異なります。今回の記事で紹介するのは主に相続法改正についてです。
まず相続の基本をおさらい
相続法改正のポイントを知る前に、まずは相続制度の基本をおさらいしておきましょう。相続とはある人が亡くなった時の財産を配偶者や子どもが受け取ることです。
相続では、財産のことを遺産、亡くなった人を被相続人、財産を受け取る人を相続人、と呼びます。なお、金銭や不動産のように一眼でわかるものだけでなく、被相続人の権利や義務も遺産の一部です。
相続の方法は、大きく分けると、遺言書による相続、遺産分割協議による相続の2つがあります。法定相続分とは、民法で決められた人(法定相続人)が受け取る相続割合のことで、例えば相続人が配偶者と子どもであれば法定相続分はそれぞれ1/2です。
遺言書がある場合、原則として被相続人が遺した遺言書の内容に基づいて相続されることになります。これが、遺言書による相続です。遺言書にも様々な形式があり、代表的なのが公正証書遺言、秘密証書遺言、自筆証書遺言です。
なお、全部が遺言書の通りになるわけではなく、兄弟姉妹以外の法定相続人は一定の割合までは「遺留分」として受け取りを主張することができます。遺留分で受け取れる割合は基本的に法定相続分の1/2です。
ここまで相続として説明しましたが、相続と似た用語として遺贈という言葉があります。遺贈とは遺言書に基づいた財産贈与のことです。
遺産分割協議による相続では、相続人全員が協議して遺産の分割方法を決めます。金融機関で預金などの相続をする際、遺言書がなければ遺産分割協議書を作成することが多いです。
改正内容は法務省資料で確認できる
実際にこの法律を読んでみると改正内容を確認することができますが、少しわかりにくいかもしれません。その場合は、法務省のHPで改正に関する資料を発表しているので参考にしてください。
開始時期や条文内容は以下の通りです。
開始時期
民法改正のポイントとそれぞれの施行時期は以下の通りです。
・配偶者居住権の新設(2020年4月1日〜)
・婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置(2019年7月1日〜)
・預貯金の払戻し制度の創設(2019年7月1日〜)
・自筆証書遺言の方式緩和(2019年1月13日〜)
・法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設について(2020年7月10日〜)
・遺留分制度の見直し(2019年7月1日〜)
・特別の寄与の制度の創設(2019年7月1日〜)
条文内容
今回ポイントとなる条文は改正法903条、改正法909条の2、改正法1042~1049条、改正法第1050条などですが、条文内容は膨大に及ぶので、この記事では割愛します。そこで、次から紹介するのは改正の肝となる部分の各ポイントです。
1 配偶者居住権の創設

最初に紹介するのが、夫に先立たれた妻の不安解消にもつながる配偶者居住権の創設です。
配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、他の相続人が被相続人の持ち家を相続したとしても相続時にその家に住んでいた被相続人の配偶者は引き続き無償で住むことができる権利です。配偶者居住権は定めがない限り、配偶者が亡くなるまで存続しますが、譲渡やさらに相続することはできません。
配偶者居住権は所有権のように法務局で登記することにより、自らの居住権を第三者に主張することが可能です。
配偶者短期居住権もある
配偶者居住権には先ほど紹介した配偶者(長期)居住権と配偶者短期居住権があります。配偶者短期居住権は被相続人が所有する建物に引き続き一定期間住むことができる権利です。居住可能な期間は遺産分割の相続の場合、遺産分割終了時か死後6カ月経過日のいずれか遅い日、遺贈で居住建物取得者がいる場合は、取得者による権利消滅の申込の日から6カ月経過日となります。
配偶者居住権と配偶者短期居住権は似ていて紛らわしいかもしれません。大きな違いは配偶者短期居住権が相続開始時に自然に発生するのに対し、配偶者居住権は取得するために遺産分割、遺贈、死因贈与のいずれかを経なくてはならない点です。
また、配偶者短期居住権は建物に対してのみの権利ですが、配偶者居住権では相続利用開始前と同じ方法であれば店舗として使用していた部分も利用することができます。
配偶者居住権の新設によるメリット
配偶者居住権が新設されるまでは、配偶者が居住建物を取得する場合に他の財産を取得できなくなるおそれがありました。成人の子どもがひとりおり、例として夫婦で夫名義の家に住んでいたケースを考えてみましょう。
預貯金2,000万円、自宅2,000万円の資産を遺して夫が亡くなった場合、法定相続分は1/2ずつなので妻、子どもそれぞれに2,000万円の権利があります。そこで、妻は住む場所がなくなると困るので家を売りたくない、子どもは不動産を断りできるだけ多くの現金を受け取りたいとするとどうでしょうか。
妻が自宅2,000万円を取得することになるため、子どもに預貯金2,000万円全額が渡ることになります。これでは、妻がひとりで生活していくための資金が相続では得ることができず、生活に不安が残るはずです。
今回配偶者居住権が新設されたことで、妻は居住を続けながら別の財産も相続できるようになりました。つまり、妻は配偶者所有権(1,000万円)と預貯金1,000万円、子が負担付き所有権(1,000万円)、預貯金1,000万円を相続します。
すでに紹介したように、配偶者居住権は配偶者の死後消滅するので、このケースでは妻が亡くなった後に子は物件を売却可能です。
2 夫婦間の居住用不動産贈与の保護

続いて紹介するのも、配偶者の居住用不動産に関する規定です。
改正の内容
今までは、被相続人が配偶者に事前に居住用不動産を贈与していた分についても、被相続人が亡くなり配偶者が相続する際にはすでに居住用不動産を相続していたとして扱われていました。しかし、今回の改正により婚姻期間が20年以上である夫婦間での居住用不動産の遺贈又は贈与は、原則遺産の先渡しを受けたものとはならず、配偶者は相続時により多くの取り分を受け取ることが可能となりました。
特別受益の持ち戻しとは
そもそも、今まで相続の先渡しとされてきたのは居住用不動産に限りません。一部の相続人が、被相続人からの遺贈や贈与で特別に受けた利益を特別受益と呼び、遺産を分割する際に特別受益を受けた相続人はその相当分を相続分から控除されていました。これが特別受益の持ち戻しです。
改正で何がメリットか
具体例をとって、何が改正によるメリットであるかを確認します。ここで紹介するのは、先ほどと同様に預貯金3,000万円の資産を遺して夫が亡くなった場合(子どもひとり)です。ただし、今回は夫が生前妻に、自宅2,000万円別に贈与していたとします。
民法改正前は、生前の贈与も相続に含まれるので、妻が受け取るのは(3,000万円+2,000万円)×1/2-2,000万円(先渡し分)=500万円です。しかし、これでは夫が妻の老後を考慮して自宅2,000万円を渡したにもかかわらず、その趣旨が反映されませんでした。
今回の改正により、被相続人の贈与などの趣旨に従った遺産分割ができることがメリットです。上記の例では、生前の贈与は考慮されないため、妻が受け取る額は3,000万円×1/2=1,500万円で、以前より1,000万円多く受け取ることができるようになります。
3 遺産分割前に一部預金払戻し可能

次に紹介するのは、被相続人の預貯金払戻しに関する規定です。
元々相続人単独で払戻しできなかった
被相続人の死亡が確認されると、金融機関が被相続人の口座を凍結するため、正式な相続手続きが済むまで引き出しや振り込みなどをおこなうことができませんでした。そして、金融機関での相続手続きには、相続人全員が署名押印した遺産分割協議書、被相続人の出生から死亡までの謄本関連、相続人全員の印鑑証明書や戸籍謄本など用意しなくてはならない書類が多く、すぐに手続きすることは困難です。
その一方で、葬儀費用などすぐに多額のお金を用意しなければならない場面があります。この問題を解消するためにできたのが預貯金の払戻し制度の創設です。
この制度ができたことにより、預貯金が遺産分割の対象であれば各相続人は遺産分割前に一定額の払戻しをすることができます。具体的な制度は以下の通りです。
・預貯金債権の一定割合については、家庭裁判所の判断を経ずに金融機関の窓口における支払が可能
・預貯金債権に限り、家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和
単独で払戻しできる額の計算方法
すでに述べた通り、払戻しが可能なのは全額ではなく、あくまで一定額です。単独で払戻しできる額は以下のように算出されます。
(相続開始時の預貯金債権の額(口座基準))×1/3×(当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分)
ここでは遺産の預貯金額が600万円で法定相続人が配偶者A、子B、子Cの場合を考えます。法定相続分はAが1/2、B、Cが1/4ずつです。
BとCで葬儀費用を下ろそうとした場合、600万円×1/3×1/4×2という式から、最大100万円まで払い戻しできます。ただし、1つの金融機関から払戻しが受けられるのは150万円までです。
4 遺言書の扱いも変わる

遺言書の取扱についても、いくつかの変更点があります。
自筆証書遺言の方式が緩和される
自筆証書遺言を作成する場合、全ての文言を自書しなければなりません。つまり、財産目録も全て自分で書かなくてはいけないということです。
民法改正により、財産目録についてはパソコンで作成することや通帳のコピーを添付することが可能になりました。これは指定する財産が多ければ、大きなメリットです。
ただし、各ページに本人が署名押印をしなければなりません。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
自筆証書遺言という言葉が出てきたので、ここで公正証書遺言との違いについて説明しておきます。自筆証書遺言は全て自分で書くのに対して、公正証書遺言では公証人が作成する点が特徴です。
自筆証書遺言はいつでも気軽に書ける点がメリットですが、作成に不備があると無効になる点、紛失の危険性がある点などはデメリットです。一方、公正証書遺言では手間や公証人の手数料が発生しますが、無効になりにくく紛失の危険性もありません。そして、自筆証書遺言のデメリットを軽減するのが次に説明する法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設です。
ちなみに、遺言のなかには、遺言書を作成した上、公証人と証人に確認してもらう秘密証書遺言というものもあります。公証役場には作成の記録のみで内容は残らず、秘密にすることができるので誰にも知られたくない遺言がある場合に適していますが、あまり利用されていないのが現状です。
自筆証書遺言の保管制度
新設されたこの制度では、自筆証書遺言を作成すると本人が指定の法務局に行けば遺言書の保管を申請することができます。遺言者が亡くなったあと、相続人は遺言書が保管されているかの確認や、遺言書の写の交付請求、閲覧が可能です。
なお、本来自筆証書遺言では遺言書の形状や加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止する検認という手続きを家庭裁判所に請求しなければなりません。しかし、遺言書保管所に保管されている遺言書は家庭裁判所の検認が不要です。
5 遺留分制度の変更

次に紹介するのは遺留分制度の変更についてです。
現行制度の問題点
冒頭でも少し紹介しましたが、遺留分とは亡くなった被相続人の兄弟姉妹以外の近しい関係にある法定相続人に最低限保障される遺産取得分のことで、遺言書の内容よりも優先されます。配偶者や子ども、孫などの「直系卑属」、親、祖父母などの「直系尊属」が遺留分を認められる相続人の範囲です。しかし、遺留分制度にはいくつかの問題点がありました。
例えば、遺留分減殺請求権の行使によって、土地建物などに共有状態が生ずることがあります。被相続人が経営者の場合、後継者の長男と経営に携わっていない長女が会社の土地建物を共有することになってしまい、事業承継がしにくくなる点が問題です。また、共有割合は財産の評価額によって決まるため、1/2や1/3といった単純な割合ではなく分母・分子の大きい複雑な共有状態になります。
遺留分減殺請求権が遺留分侵害額請求権に変わったのが今回の制度の変更点です。つまり、遺留分を侵害された場合、遺贈や贈与を受けた者に対して遺留分侵害額に相当する金銭の請求ができます。
さらに、遺留分侵害額請求権を受けた側からみると、今回の民法改正により、遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合、裁判所に支払期限の猶予を求めることが可能となりました。
変更によるメリット
不動産が遺贈等されたことにより遺留分を侵害された場合、その代わりとして金銭を請求できるため、複雑な共有関係が必ず生じるという状態を回避することができます。つまり、先ほど紹介した例では長男が会社の土地建物を所有し、長女は侵害された分を金銭で請求するということが可能です。これにより、長男にスムーズに事業承継させたいという被相続人の意向も尊重することができます。
6 介護等の貢献が特別の寄与になる

最後に解説するのは、特別の寄与についての制度です。
現行制度の問題点
親の介護は家族みんなで協力して進めるに越したことがありませんが、実際問題として特定の人に負担が偏ってしまうことが多いです。例えば、長男夫婦が母親と同居し、特に妻が義理の母親の面倒を見ていた場合を考えてみます。
万が一長男が母親より先に亡くなってしまい、その半年後に母親が亡くなると、長男の妻が一手に介護を引き受けていたとしても母親の財産を相続できるのは健在する母親の子(例えば長女、次女)だけです。寄与分制度として生前に無償で介護や看護などをしていた相続人は相続時に上乗せすることができますが、どんなに介護していても法定相続人にあたらない長男の妻は全く財産を取得できないことになり、不公平感が指摘されていました。
今回の改正により、相続人以外の被相続人の親族(今回は長男の妻)が無償で被相続人の療養看護等を行った場合、相続人(ここでは長女、次女)に対して金銭の請求できるようになります。これが特別寄与料制度です。
変更によるメリット
特別寄与料制度が創設されたことで、介護などの貢献をしていた人が報われるという点がメリットです。ただし、特別寄与料制度を利用した際の対価の判定法についてはまだ詳しく決まりがないため、今後争点となる可能性はあります。
内縁の妻は該当しない点に注意
なお、今回の改正で対象になるのはあくまで被相続人の親族であり、さらに法律婚を前提としています。長男の内縁の妻や被相続人の内縁の連れ子は対象になりません。
そのほかのポイント

今回紹介した民法改正には、そのほかにもいくつかポイントがあるので紹介します。
相続による移転登記の義務化
相続の登記についてはすでに触れましたが、ここで詳しく解説しておきます。相続(による所有権移転)登記とは、所有者が死亡した不動産について、誰に所有権が移転したかを明確化させる手続きです。
2020年10月時点では、所有権移転登記を相続人に義務化する法律は整備されていません。しかし、現在日本には登記簿で現在の所有者を確認できない土地が多く存在し、政府も問題視しています。
このような所有者不明の土地の多くが管理者も存在しないため、景観悪化や近隣住民への迷惑につながる点が問題です。政府は「所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針」や「経済財政運営と改革の基本方針2018」で2020年までに必要な制度改正を実現するとうたっているので、遅くとも2021年には国会に関連法案が提出されるのではないでしょうか。
なお、相続登記が義務化されていないからといって、そのままにしておいて良いわけではありません。民法改正によって第899条の2第一項が新設され、「相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができない」とされています。
ここで紹介するのは、親の死後姉弟で相続トラブルが生じ、弟が勝手に不動産を第三者に売却したというケースです。姉弟が相続で揉めている事情を第三者が知らずにこの不動産を購入し登記すれば、姉は相続分を超える部分については第三者の所有権を否定することができません。たとえ、親の遺言書に全所有権を姉に相続すると書かれていたとしても否定できないのです。
相続登記は現段階では義務化されていませんが、今後義務化の見込みが高い点や上記のトラブルを避けるためにも、相続登記は早めにしてください。
相続税制度への影響
今回紹介した民法改正は、相続税制度にも影響があるのでしょうか。まず、成年となる年齢を20歳から18歳に引き下げられたことから、相続税の未成年者控除の対象となる相続人の年齢を20歳未満から18歳未満に引き下げ、相続時精算課税制度をはじめとする各特例の受贈者の年齢要件を20歳以上から18歳以上に引き下げるなどの変化があります。
また、配偶者居住権の相続税評価額や特別寄与料に対しても課税されることもおさえておいてください。
まとめ

今回紹介したように、民法改正により相続の制度が大きく変わりました。配偶者の特例や預金払戻しに関する扱いなど、知らなければつい見逃してしまうこともあります。
ポイントを把握し、相続の段階になった時に慌てないようにしてください。また、遺留分制度の変更のように、個人単位だけでなく事業承継などにも関係してくる変更もあります。
事業承継を検討している人は、この相続制度の変更点だけでなく、承継のタイミング、資金調達方法、後継者確保など考えなくてはならない事柄が多いです。そこで、何から始めれば良いかわからない時は公認会計士や弁護士などM&Aに精通している専門家に相談してください。
M&A DXのM&Aサービスでは、大手会計系M&Aファーム出身の公認会計士や金融機関出身者等が多数在籍しています。事業承継でお悩みの方は、まずはお気軽にM&A DXの無料相談をご活用下さい。